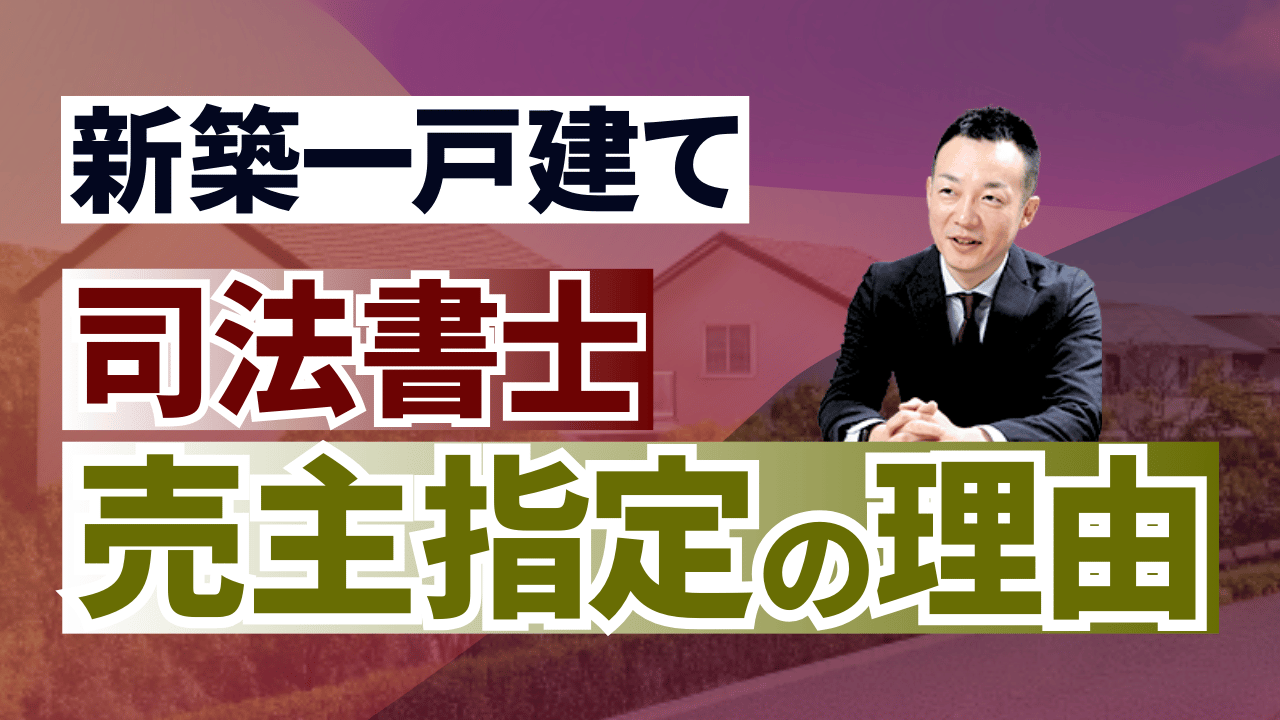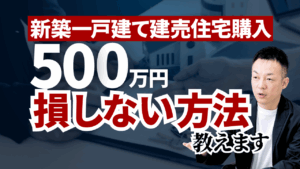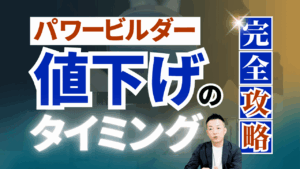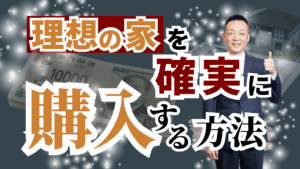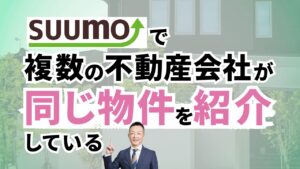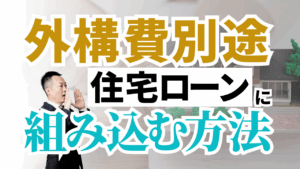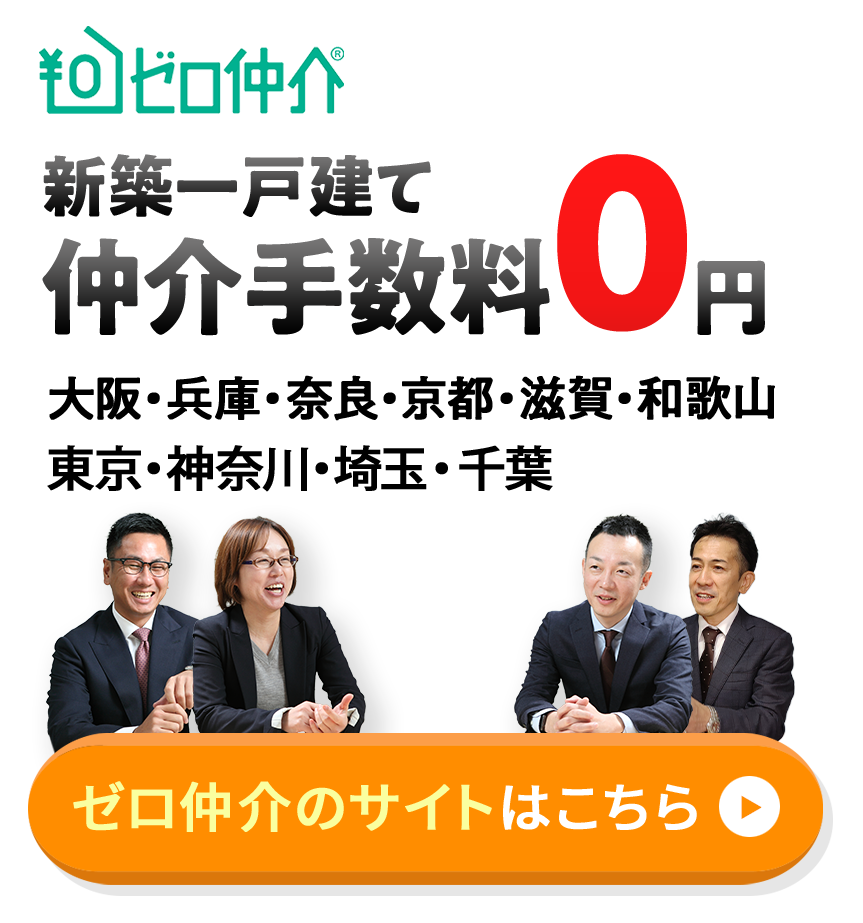こんにちは、ゼロ仲介の鈴木です。
不動産チラシの右下あたりに、物件の引渡し日などが記載されている、ちょうどその下くらいの備考欄に「※司法書士は売主指定」と記載されているのを見たことはありませんか?
特に新築一戸建て建売住宅や飯田グループなどの物件を見ると、ほとんどに「司法書士・売主指定」の記載があります。
 ヒガシノさん
ヒガシノさんなぜ購入者である買主が司法書士を選べばれへんの?
と疑問に思う方も多いはずです。
今回は、新築建売住宅などで「売主指定司法書士」となる理由をくわしく解説します
登記手続きの基本と司法書士の役割
そもそも登記手続きは、買主または売主本人が法務局に自分で来庁して登記しても良いのは、ご存じですか?
国家試験に合格した司法書士に代理してもらわなくてもよいのです。




でも実際には、ほぼ100%司法書士に依頼します。特に住宅ローンを利用する場合は必須です
なぜかというと、住宅ローンを利用して購入する場合は、金融機関が司法書士が代理で登記手続きしないと融資してくれません。
銀行融資を利用しない個人間売買でも売主や買主の必要書類に不備があったりすると、法務局の登記手続きがストップしてしまうこともあります。




売買代金を売主に支払ったのに登記完了できないとか、そんなん考えたら怖すぎるわ
その通りです。なので、新築建売住宅の購入ではほぼ100%司法書士に依頼します。
問題は「誰が指定する司法書士に依頼するのか」ということです。
新築建売住宅の場合は売主指定が一般的
不動産取引における司法書士選定には、実は地域差や物件タイプによる違いがあります。
関東地区では一般的に次のようなルールがあります。
- 「中古物件は買主側」
- 「新築物件は売主側」




これは暗黙の了解で、業界ではほぼ当たり前のルールです
中古物件の場合、一番費用負担の大きい「売主から買主への所有権移転登記」は買主が負担します。そのため、買主が司法書士を指定するのが一般的です。
一方、新築の建売住宅や分譲マンションの場合は、売主である建売・分譲業者が司法書士を指定することがほとんどです。




飯田グループの建売物件を見てたんやけど、全部「司法書士・売主指定」になってたわ。自分では選ばれへんの?
飯田グループホールディングスのような大手住宅メーカーでは、ほぼすべての取引で売主指定の司法書士が設定されています。
これは業界の標準的な慣行なので、基本的には変更できないと思ったほうがいいです。




「変更できない」と言われると、なんかあやしいと思いますよね。でも実は合理的な理由があるんです
売主指定の司法書士となる合理的な理由
なぜ新築建売住宅では売主指定の司法書士が一般的なのでしょうか。
これには納得できる理由があります。
① 大量販売による効率性
建売住宅にせよ、分譲マンションにせよ、販売戸数が多いという特徴があります。
中古物件の売買は1つ1つの物件ごとですが、新築分譲は複数の物件をまとめて販売します。
例えば、飯田グループなどは数十戸、数百戸という単位で建売住宅を建築・販売しています。




これを毎回バラバラの司法書士に頼むと、事務手続きがめちゃくちゃ煩雑になるんです
売主である建売・分譲業者は権利証(所有者であることを照明する書類)を管理しており、物件を仕入れた際の金融機関からの借入に関する担保の抹消手続きなども必要です。
これらの手続きをバラバラの司法書士が担当していたら、権利証の管理や金融機関との手続きなど、事務作業が煩雑になり効率が悪くなります。
② 権利証の安全な管理
特に建売分譲などで複数の住宅を建設・販売する場合、登記識別情報(権利証)を安全に管理する必要があります。




ふーん、なるほど。権利証って大事な書類やもんな。紛失したらえらいことになりそう。。
その通りです。同じ司法書士に依頼することで、紛失などのトラブルを防ぎやすくなります。
③ 金融機関との関係
建売会社も事業融資を利用して物件を建設しているため、金融機関によっては司法書士を指定することがあります。
特に地方銀行との取引では、この傾向が強いとされています。
④ 取引の円滑化
同じ司法書士に依頼することで、取引がスムーズに進むメリットもあります。
建売会社や分譲会社は年間を通じて多くの物件を取り扱うため、特定の司法書士と連携することで手続きの標準化や効率化が図れます。




裏話をすると、昔は「キックバック」という話も業界ではあったんです。売主指定の司法書士から建売会社などに報酬の一部が戻ってくる仕組みです
でも、これ完全に違法なんです。
現在はほとんどありませんし、飯田グループなどの大手メーカーでは、そういった不正はないと考えて大丈夫です。
売主指定司法書士の報酬と費用相場
登記費用は、登録免許税という税金と司法書士による報酬の合計額です。
司法書士の報酬額は自由設定となっており、不動産仲介手数料のように上限額が決まっているわけではありません。
そのため、司法書士によって登記費用は異なる可能性があります。




一般的な登記費用の相場を言うと、建物が一つで1筆、土地が1筆の場合、1筆あたり2万円〜7万円くらいです
安い司法書士では1筆2万円から、高い司法書士では7万円というところもあります。
土地が複数筆に分かれていると、さらに費用がかかることもあります。




けっこう幅があるんやな。飯田グループとかが指定する司法書士の報酬って、高いんかな?
売主指定司法書士の場合、建売会社や分譲会社と継続的な取引関係があるため、費用面で特別に高額になるということはあまりないのが一般的です。
大手の建売会社は年間多くの物件を取り扱うため、司法書士との間で一定の報酬体系が確立されていることが多いです。




まれに高額な報酬を請求する司法書士もいますので、事前に費用の見積もりを確認しておくことをおすすめします
買主としての対応と心構え
新築一戸建て建売住宅では売主指定司法書士が一般的であることを理解した上で、買主としてどのように対応すればよいのでしょうか。
① 契約前の確認
売買契約書には「買主は、所有権移転登記を売主の指定する司法書士に依頼するものとする」という司法書士指定特約が含まれることが多いです。




飯田グループなどの大手ハウスメーカーでは、この特約がほぼ標準で入っています。これは業界の慣行として受け入れられており、変更を求めるのは難しいのが実情です
② 登記費用の確認
売主指定の司法書士であっても、登記費用の見積もりを事前に確認することはできます。




売主指定やからって、言われるがままに高い費用払うのはアカンやんな?
その通りです。相場から大きく外れた金額を請求されるようであれば、その理由を尋ねてみるのも良いでしょう。
③ 質問する姿勢
不明点があれば、遠慮せずに質問することが大切です。
売主指定の司法書士であっても、最終的に費用を負担するのは買主ですから、サービス内容についての説明を求める権利があります。




「売主指定だから」と言われても、費用の内訳をきちんと説明してもらう権利は買主にあります
まとめ
いかがでしたでしょうか。新築一戸建ての建売住宅を購入する際、司法書士が売主指定となるのは、業界の慣行としてかなり一般的なことです。
特に飯田グループなどの大手ハウスメーカーでは、ほぼ標準的な取引形態となっています。
これには、大量の物件を効率的に管理するためや、権利証の安全な管理、金融機関との関係など、合理的な理由があります。
売主指定司法書士による登記手続きは、新築建売住宅購入における標準的なプロセスの一部として、受け入れるべきものと言えるでしょう。
ただし、費用の内訳については透明性を求め、相場から大きく外れた報酬を請求されないよう、注意することは買主の権利です。




実は新築一戸建て購入の際には、司法書士費用以外にも「仲介手数料」という大きな費用がかかります。でも、ゼロ仲介なら仲介手数料が0円で、この費用を完全に節約できるんです
マイホーム購入は人生の大きな買い物です。賢く手続きを進めることで、物件価格の約3%(100万円近く)の仲介手数料を節約できます。




えっ!そんなに節約できるん?どうやって?




ゼロ仲介では、買主からは一切手数料をいただかず、売主からの仲介手数料のみで運営しています。しかも、ローン事務代行手数料も不要なので、他社で10万円~30万円かかる費用もさらに節約できます
- LINEでいつでも気軽に相談可能(最短5分で返信)
- 住宅ローンの専門家による最適プラン提案(関西の全金融機関の審査基準を把握)
- 物件価格の交渉サポート
- 大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・和歌山、さらに東京・神奈川・埼玉エリアにも対応
登記手続きを含めた取引の流れを理解し、かしこく安心して住宅購入を進めたい方は、ぜひLINEでお気軽にご相談ください。