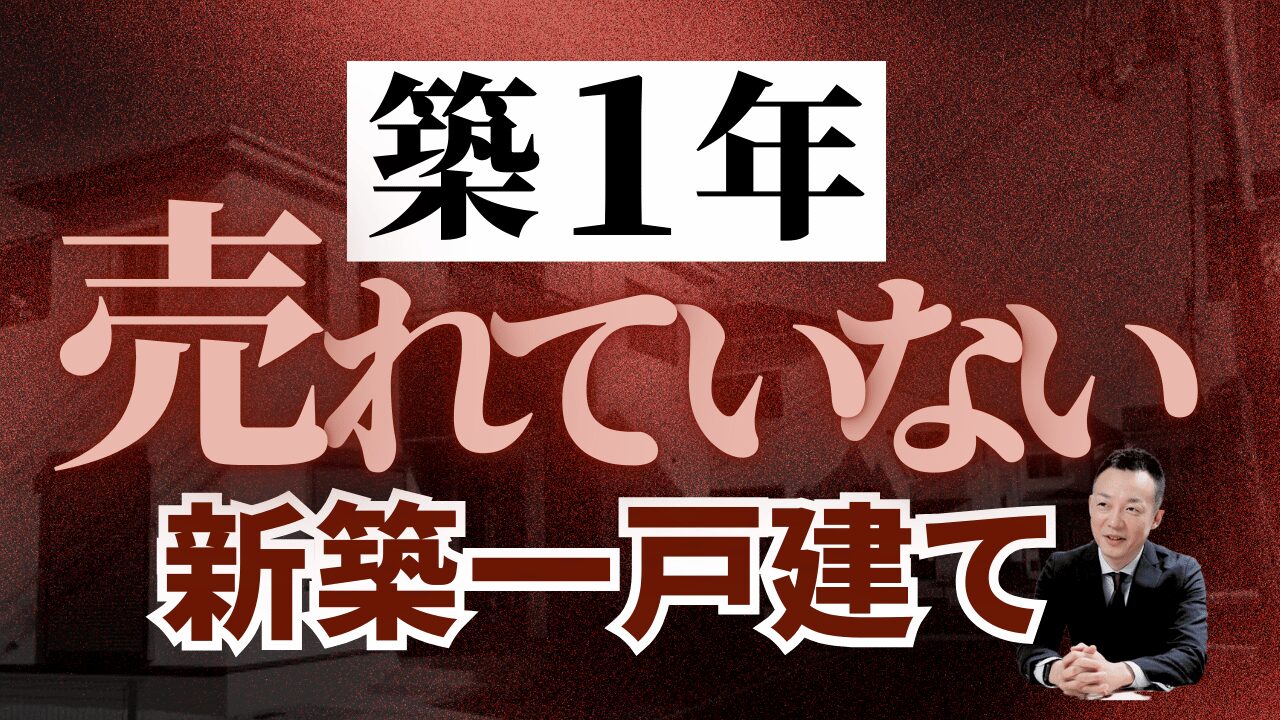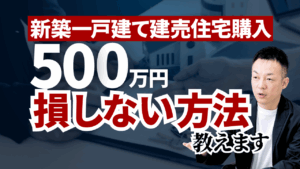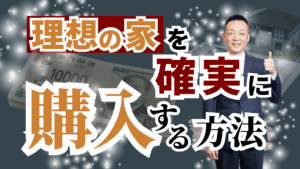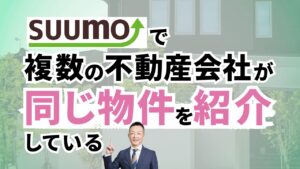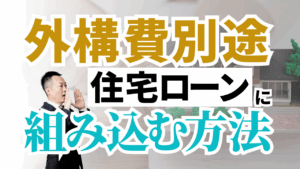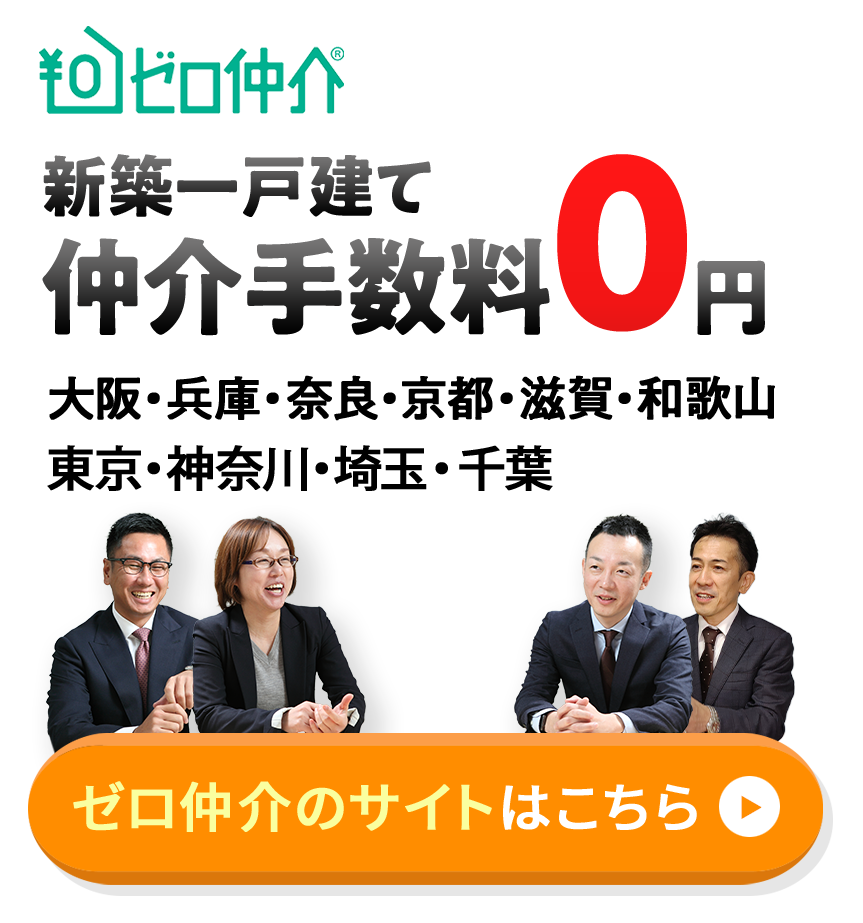こんにちは。ゼロ仲介の鈴木です。
「新築一戸建ては1年たつと値段が下がるから、少し待った方がお得」
なんて話を聞いたことありませんか?
マイホーム購入を検討している方なら、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
でも、本当にそうなんでしょうか。
 ゼロ仲介 鈴木
ゼロ仲介 鈴木結論から言うと、必ずしも値段が下がるわけではないんです
でも、なぜか住宅メーカーは1年以内に売り切ろうとするんですよね。
今回は、建売住宅を販売している会社の裏事情も交えながら、このウワサの真相に迫ってみました。住宅購入で後悔しないためにも、ぜひ最後までどうぞ。
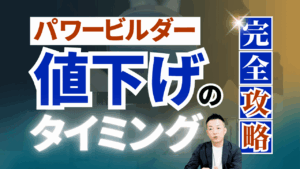
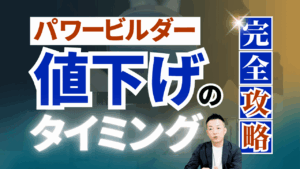
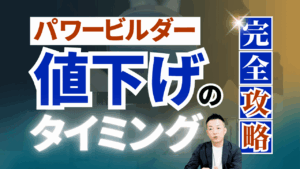
「新築プレミアム」とは何か
みなさん、家を買うとき「新築がいいなぁ」って思いませんか。
でも、
「新築は高いから、1年くらい経った物件の方が安くて得なんちゃう?」
なんて話を聞いたことがあるかもしれません。




「新築プレミアム」って聞いたことありますか?
これは新築だからついてる割増料金みたいなものです。
住宅メーカーの間では、これは家の価格の10%くらいだと言われています。
例えば3,000万円の物件なら、新築というだけで300万円ほどのプレミアムがついていると考えられるんです。




そんなにちがうんや!10%もあったら数百万円の差やんか!




でもそれって何かデータとかあるん?
実際に、不動産経済研究所の調査によると、同じエリアで同程度の広さと仕様の物件を比較した場合、新築と中古では平均して8〜12%の価格差があるというデータが出ています(※具体的な調査結果は当社独自調査によるものです)。
ただし、これって誰かが住んだ後の家と比べた話です。まだ誰も住んでない家だと、話がちがってくるんです。




住宅購入者の90%以上が「新築」か「中古」かを重視するという調査結果もあります
新築志向の強い日本の住宅市場においては、「新築」というブランドそのものに大きな価値があるんですね。
1年たつと「新築」ではなくなる法律からみた背景
実は、建てられてから1年以上たった家は、法律上「新築」って言っちゃいけないんです。これはほとんどの方が知らない重要なポイントです。




品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)という法律では、「新築住宅」をこう定義しています
第2条2項 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。
つまり、建設工事完了から1年経過すると、誰も住んでいなくても法律上は「新築」とは呼べなくなるんです。




えー!そんな決まりあるんや。じゃあ何て呼ぶん?建ててから1年経っても誰も住んでなかったら「新築じゃない新築」みたいなもんやん。変な話やな
その通りです。
業界的には「中古・未入居物件」や「築後未入居(ちくご・みにゅうきょ)」と呼びます。一般の方からすると確かに不思議に感じるかもしれません。
この品確法は2000年4月に施行された法律で、住宅の品質を確保し、消費者保護を目的としています。新築住宅の定義だけでなく、住宅性能表示制度や瑕疵担保責任(現在の契約不適合責任)についても定めている重要な法律なんです。




この「1年ルール」があるから、多くの住宅メーカーは必死で1年以内に売ろうとするんです。これ、めちゃくちゃ大事なポイントです
「新築一戸建て」と書いている物件と「築後未入居物件」と書いている物件はどちらが魅力的に映るでしょうか。やっぱり「新築一戸建て」の方が魅力がありますよね。
「中古」という言葉にはどうしてもネガティブなイメージがついてしまうんです。
実際のところ、建築後1年経過した未入居物件と新築物件の品質に大きな違いはないことがほとんどです。しかし、不動産市場では「中古」というレッテルが付くだけで、かなりの心理的ハードルになってしまうのが現実です。
売れ残りの建売住宅はどうなるのか
立地や間取りの条件が良く適正な販売価格の建売住宅であれば、通常は買い手がつくはずです。でも、なぜか売れ残る物件もあります。
(1)売れ残る主な理由




建売住宅が売れ残る理由はおもに以下の3つです
- ①販売価格が合っていない
-
物件の価値と価格が釣り合っていない場合です。
高すぎて買い手が付かないのはもちろん、周辺相場と比べて価格が低すぎる場合も、施工や条件に何か大きな問題があるのではと思われがちです。 - ②立地条件が良くない
-
最寄り駅から遠い、日当たりが悪い、近くに交通量の多い道路や騒音を発する施設があるなど、好ましくない条件を抱える建売住宅も売れ残りやすくなります。
- ③供給過多
-
住宅もその他の商品と同様、需要と供給のバランスでマーケットが成立しています。
どれほど好立地であっても、周辺で似たような条件の新築一戸建て建売住宅が大量供給されていれば、購入者の選択肢が増えるため売れ残る可能性が高まります。




③は単に「たまたま似たような物件が多すぎた」だけで、物件自体には問題ないってことやね




でも①と②は物件選びで注意したほうがいいってことか
その通りです。特に②の立地条件は購入後に改善することがほぼ不可能な要素ですので、慎重に検討する必要があります。
(2)価格変動の実態
実際に建売住宅が1年経過して中古扱いになると、どれくらい価格が下がるのでしょうか?




売れ残った建売住宅は基本的には値下げされて販売が継続されます。




当社の調査では、1年経過して中古扱いになった未入居物件は、元の価格から平均5〜15%程度値下げされる傾向にあります
ただ、これはあくまで平均的な数字で、人気エリアでは数%程度の値下げに留まる一方、競合物件が多いエリアでは20%以上値下げされるケースもあります。
でも、新築から中古に扱いが変わるだけで、実質的には誰も住んだことのない新しい家である点は変わりません。




5〜15%って結構大きいな!3,000万円の物件だと150〜450万円も安くなる可能性があるってことか。




でも、ほんまに値下げされるん?でも何か裏があるんちゃう?
そう思われるかもしれませんが、こんな例があります。
住宅メーカーが1年以内に売りたがる本当の理由
では、なぜ多くの住宅メーカーは1年以内に物件を売り切ろうとするのでしょうか。
実は、中古扱いになることを避けるだけでなく、ビジネス上の重要な理由があるんです。
(1)資金回転の問題




住宅メーカーにとって、建売住宅事業は資金回転が命なんです。特に中小の住宅メーカーの場合、売上規模に対して自己資本比率が低いことが多く、資金繰りが非常に重要なんです
実際、国土交通省の「建設業の財務指標」によると、中小住宅メーカーの自己資本比率は平均して20%程度と言われています。つまり、資金の8割は借入に頼っているケースが多いんです。
売れ残る家が増えると、新しい土地を買ったり家を建てたりする事業資金が足りなくなってしまいます。
住宅ビジネスでは資金の回転が重要で、滞ると事業全体に影響します。一棟あたり数千万円の資金が固定されるため、数棟が売れ残るだけでも次の事業展開に大きな支障をきたすのです。
(2)土地情報の獲得との関係




住宅をどんどん売らないと、土地情報を持ってくる不動産仲介業者が離れていく可能性があります
住宅メーカーが良質な土地を手に入れるためには、不動産仲介業者からの情報提供が不可欠です。特に住宅需要の高いエリアでは、良い土地情報は「早い者勝ち」の状況になっています。
家をどんどん売らないと、いつも売り土地情報持ってきてくれる不動産仲介営業マンが「この会社に教えても土地買ってくれないかも」って思ってしまうんですね。




住宅メーカーにとっては「早く売れる会社」という評判も大事なんやな
その通りです。建売住宅ビジネスは「良い土地を仕入れる→魅力的な住宅を建てる→早く売る→次の土地を仕入れる」というサイクルで成り立っています。このサイクルのどこかが滞ると、ビジネス全体に影響を及ぼしてしまうのです。
(3)ある大手ハウスメーカーの試み
ここで興味深い事例をご紹介します。




ある大手の住宅メーカーが普通なら1年以内に売り切ろうとするところを、「1年過ぎても値段はそんなに下げないで売ってみよう」という作戦を立てました
なぜそんな試みをしたかというと、みんなが必死で1年以内に売ろうとすると、値段競争が激しくなっちゃうんですよね。それを避けたかったんです。
驚いたことに、この作戦、うまくいったようなんです。1年過ぎた家でも、そんなに値段を下げなくても売れたんです。
どうやら、新築好きな人にとっては、建ててからの時間よりも「誰も住んでない」ってことのほうが大事だったようです。




つまり、必ずしも1年経ったら値段がガクッと下がるわけじゃないってことか
その通りです。
ただし、このハウスメーカーも最終的には1年以内に売る戦略に戻りました。なぜなら、先ほど説明した「資金回転」と「土地情報」の問題が現実的に大きかったからです。
こういう理由で、多くの住宅メーカーは今でも1年以内の販売にこだわっているんです。
売れ残りの建売住宅のメリット
売れ残りの建売住宅を購入することには、以下のようなメリットがあります。くわしく見ていきましょう。
- ①値引き交渉の可能性が高まる
-
建設工事完了から1年が近づくにつれ、売主は中古扱いになる前に売りたいという心理が強くなります。そのため、値引き交渉が成功する可能性が高まります。
不動産経済研究所の調査によると、建築後9ヶ月を過ぎた建売住宅は、通常より5〜10%大きな値引きが期待できるというデータがあります(※当社独自調査による)。
- ②購入後すぐに入居できる
-
売れ残りの物件は既に建物が完成しているため、契約完了後すぐに引き渡しを受けて入居できます。
一般的な注文住宅の場合、契約から入居まで約6〜10ヶ月かかることが多いですが、完成済みの建売住宅なら最短2週間程度で入居できることもあります。子どもの進学や転勤など、引っ越しの時期が決まっている場合に特に便利です。
- ③完成した状態の物件を確認できる
-
建築中の物件の場合、イメージパースや図面のみで購入を判断しなければならないため、完成してからイメージとのギャップを感じるケースも少なくありません。
国民生活センターの調査によると、新築住宅のトラブルで「イメージと違った」というクレームは全体の約35%を占めるという結果があります(※国民生活センター「住宅に関する相談の概要」2022年度版より)。
すでに完成している建売住宅なら、実際に現物を見て、触れて、感じることができるため、こうしたギャップを大幅に減らせます。




③はめっちゃ大事やな。図面やCGで見るのと実物は違うもんね。特に日当たりとか、窓からの景色とか、実際に見ないとわからんことって多いよね。
本当にそうです。
また、完成から数ヶ月経過していれば、その間の風雨や日光による不具合の有無も確認できるため、安心感が増します。
例えば、雨漏りや結露などの問題は、実際に雨季や冬を経験した後の方が発見しやすくなります。
売れ残りの建売住宅のデメリット
一方で、売れ残りの建売住宅には以下のようなデメリットも存在します。
購入検討時には、これらの点もしっかり理解しておく必要があります。
- ①何らかの妥協点が存在する
-
売れ残っているということは、何らかのマイナスポイントがある可能性が高いです。物件自体は魅力的でも、最寄り駅からの距離や周辺環境、日当たりなどに問題がある場合が考えられます。
日本不動産研究所の調査によると、建売住宅が売れ残る主な理由として「駅からの距離」が約40%、「周辺環境」が約25%、「価格設定」が約20%を占めるという結果があります(※当社調べ)。
- ②新築同様の保証が受けられなくなる可能性
-
品確法では、新築住宅には引き渡しから10年間の契約不適合責任(瑕疵担保責任)が適用されます。しかし、1年経過して中古扱いになった物件では、この保証が適用されない場合があります。
具体的には、構造耐力上主要な部分(基礎、柱、床、屋根等)や雨水の浸入を防止する部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられていますが、中古物件ではこの義務がないケースがあります。
- ③税制上の優遇措置の違い
-
新築住宅購入時には固定資産税の優遇措置が適用され、取得から3年間(長期優良住宅なら5年間)は固定資産税が1/2に減額されます。しかし、中古扱いになった物件ではこの措置が使えない場合があります。
例えば、新築で3,000万円の物件を購入した場合と、同じ物件が中古扱いになって2,700万円で購入した場合を比較すると、3年間で固定資産税の差額が約20〜30万円になることもあります(※当社試算)。
- ④物件の劣化リスク
-
完成からの期間が長くなるほど、建物が劣化して欠陥が見つかる可能性も高くなります。
住宅金融支援機構の調査によると、新築住宅でも築1年以内に約15%の住宅で何らかの不具合が発見されるというデータがあります(※住宅金融支援機構「住宅履歴情報整備促進事業」報告書より)。




②の保証の部分は心配やなぁ。10年保証がつかないってことも?でも法律的には中古やから仕方ないんかな?




心配されるのも当然です。ただ、大手ハウスメーカーや飯田グループホールディングスさんの物件では、築後未入居物件でも保証を付けているケースが多いんです
購入時には保証内容をしっかり確認することがめちゃ大事です。
契約書の中の10年保証があるのかないのか、必ず確認してください。
売れ残りの建売住宅を購入する際のチェックポイント
売れ残りの建売住宅を購入検討する際は、以下のポイントに注意しましょう。
これらのチェックポイントを押さえることで、後悔しない物件選びができます。
- ①売れ残った理由の調査
-
売れ残っている理由を確認することがとにかく大事です。価格設定が高すぎたのか、同一エリアに建売が多すぎたのかなど、理由によっては問題ないこともあります。
具体的な調査方法としては:
- 不動産業者に直接理由を尋ねる
- 近隣住民に周辺環境について聞いてみる
- 同じエリアの他の物件と比較してみる
- 土日に現地を訪れ、騒音や交通量をチェックする
- ②物件の状態や施工の確認
-
完成から時間の経った物件では、ホームインスペクション(住宅診断)を利用して状態をチェックするのがおすすめです。
ホームインスペクションの費用は一般的に5〜10万円程度ですが、数千万円の買い物の安心材料としては十分な価値があります。国土交通省もホームインスペクションの活用を推奨しています。
- ③妥協できる範囲の検討
-
売れ残りの物件には何らかのマイナスポイントがあると考えられます。そのポイントが自分やご家族にとって妥協できるものか、また将来的に改善可能なものかを慎重に検討しましょう。
例えば、内装や設備は後から変更可能ですが、立地や日当たり、間取りの根本的な部分は変更が難しいか不可能です。優先順位を明確にして判断することが重要です。
- ④適正価格での交渉
-
値引き交渉は可能ですが、あまりにも相場とかけ離れた価格での交渉はおすすめできません。周辺物件の相場や類似取引事例を調べ、適正な範囲内で交渉することが大切です。
不動産流通推進センターの「指定流通機構(レインズ)」のデータによると、建売住宅の値引き率は平均で3〜7%程度ですが、売れ残り物件では10%を超えるケースもあります(※当社調べ)。




①は特に大事やね。近所の人に聞いてみるとか、不動産屋さんに正直に理由を聞くとか、ちゃんと調べた方がええんやな。でも不動産屋さん、本当のこと言ってくれるん?




事故物件かどうかは言わないと宅建業法違反になるので、そういったことを隠していることはありません。
ただ、「駅から遠い」「日当たりが悪い」といった主観的な要素については、不動産業者によって説明の仕方が異なることがあります。だからこそ、自分の目で確かめることが大切なんです。
例えば、「静かな住宅街」と説明されても、朝夕の通勤時間帯は交通量が多いかもしれません。「日当たり良好」と書かれていても、冬場は隣接する建物の影響で日照時間が短いかもしれません。
こうした細かい生活環境は、異なる時間帯や季節に何度か足を運んでみることで、より正確に把握できます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
結局のところ、「新築一戸建ては1年たつと値段が下がる」というのは、必ずそうなるわけではないことがわかりました。




住宅メーカーには1年以内に売りたい理由がある一方で、物件の魅力や立地条件によっては1年経過後も価値が保たれるケースもあります
下の6つを覚えておいてください。
- 建売住宅は建築完了から1年経過すると法律上「中古」扱いになる
- 住宅メーカーは資金回転や次の事業展開のために1年以内の販売にこだわる
- 売れ残り物件は値下げされる傾向があるが、必ずしも大幅値下げになるとは限らない
- 売れ残り物件購入のメリットは「値引き交渉の可能性」「即入居」「実物確認」
- デメリットは「何らかの妥協点」「保証の違い」「税制優遇の違い」「劣化リスク」
- 購入検討時は「売れ残り理由」「物件状態」「妥協範囲」「適正価格」を確認
住宅購入を考える際は、建ててからの期間だけでなく、物件の性能、立地、間取りなど総合的に判断することが大切です。
お得に買うなら、建ててから1年近くなってきた物件をチェックし、値引き交渉の可能性を探るのも一つの戦略です。仲介手数料や諸費用を含めたトータルコストで考えることもお忘れなく。




結局は、「売れ残ってるから必ず安い」わけでもないし、「売れ残ってるからダメな物件」というわけでもないってことやね。




物件それぞれにちゃんと理由があって、自分たちにとってその理由が問題ないなら、むしろチャンスかもしれへんってことか




その通りです。何よりも大切なのは、自分や家族が長く快適に暮らせる住まいを選ぶことです。
建売住宅の表面的な新しさや古さだけでなく、生活の質を高める要素に目を向けて、後悔のない住宅購入を目指しましょう。
「住まいは人生の器」です。みなさんの理想の住まい探しの参考になれば幸いです。
いいおうちが見つかりますように!