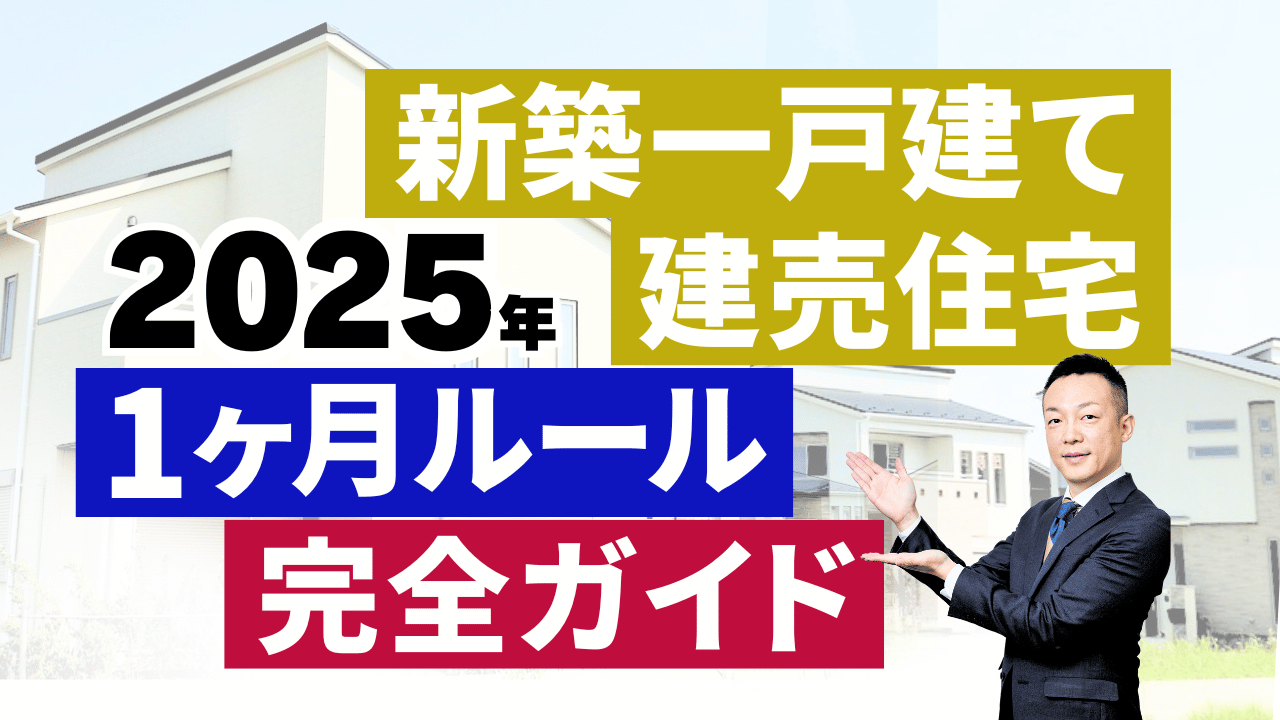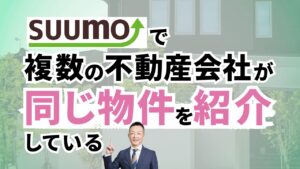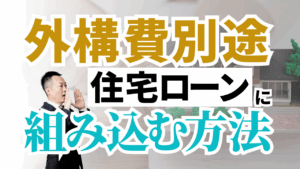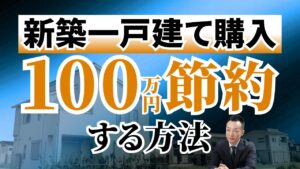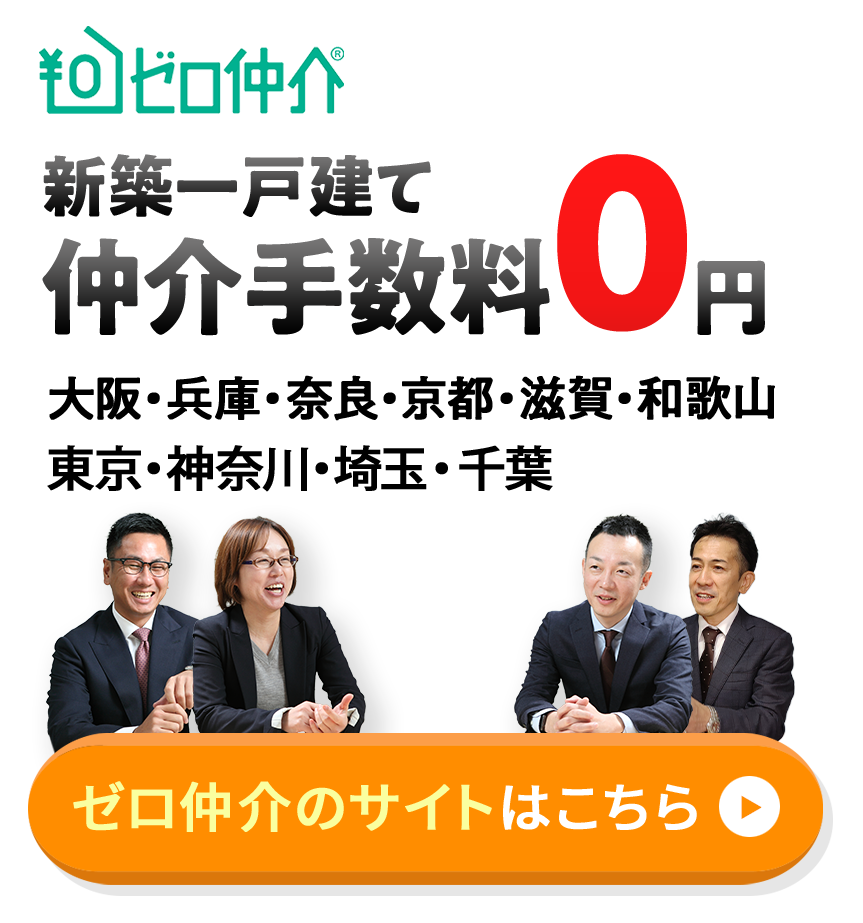こんにちは、ゼロ仲介の鈴木です。
 ヒガシノさん
ヒガシノさん新築一戸建て建売住宅を買いたいけど、なんか忙しそう




いやそもそも、そんなに忙しい?
なんて方も多いと思います。
建売新築一戸建て購入では、契約から引渡しまで1ヶ月以内というルールがある場合が多いです。
その1か月という短い期間内にいろいろな手続きをこなさなければならないため、とても忙しくなります。
今回は、建売新築一戸建て購入で日程が詰まってしまう原因の一つである、「1ヶ月ルール」について紹介していきます。
建売住宅の「1ヶ月ルール」とは何か
新築一戸建て建売住宅は売主ハウスメーカーにもよりますが、「1ヶ月ルール」がある場合が多いです。




この「1ヶ月ルール」とは、売買契約~引き渡しまでを1ヶ月以内に収めないといけないという決まりです
契約書に引き渡し期日が書かれているのですが、その期日が契約の日の1ヶ月以内に設定されるという方法で決められます。




え、そんなん聞いたことないわ。そんな短期間で全部終わらせられるん?
口約束ではなく、契約書に期日として書かれていることからもわかるように、絶対的な期限になります。
「ちょっと無理そうなんで、伸ばしてくれます?」的なテンションで伸びるものではなく、日が過ぎてしまうと契約違反になってしまいます(違約金発生)。
飯田グループなど大手ではほぼ適用される実情
特に飯田グループ系やケイアイスター不動産などの新築は、1ヶ月どころか3~4週間以内の引渡しとしている事が多いです。




「この期日は延ばせないので、銀行を変えてください」と言われることもあるほど厳格です
「5週間にしてくれないと契約しません」と言っても、「そうですか。。。残念です」と言われて、交渉決裂で終わってしまうことも。
ざっくりとですが、建売新築一戸建て購入の標準的な流れはこんな感じです。
- 不動産購入申込書(買付)を提出し、売主に受理される
- 売主と不動産売買契約を締結
- 買主負担で新築分譲住宅の表示登記を行う
- 買主は購入する新築分譲住宅に住所移転を行う
- 買主は住宅ローンを借りるための金銭消費貸借契約を締結
- 買主は売主に建物売買価格を支払い、新築分譲住宅の引渡しを受ける
このすべての手続きを1ヶ月以内に完了させなければなりません。
引渡しまでの1ヶ月間にやらないとダメなこと




そうは言っても購入する物件は決まっているし、何かやることあるん?
って思う方もいるかもしれません。
まだ引き渡しもされていないので引越し作業はできませんし。




ですが、意外と忙しくて、住宅ローンでお金を借りる手続きがたくさんあるのが実際のところです
事前審査が通った段階であれば、こんな感じの流れになります。
- 本審査が通るまでに1週間
- 金銭消費貸借契約を締結しに銀行に行って
- その●営業日後に決済できるようになります




これだけでも結構時間かかりそうやな
このように、住宅ローン手続きだけでほぼ1ヶ月まるまる使う場合がほとんどです。
こんな作業に「金消契約の時までに既存の借り入れを返済してください」なんていう融資条件がついていたりすると、その返済作業や返済の証明のための書類の発行などなど時間の必要な作業が増えてしまいます。
① 表示登記の手続き
新築分譲住宅の場合、不動産購入申込書を提出する時点では、建物に住所がありません。土地には地番という数字は割り振られていますが、建物には住所という数字は割り振られていないのです。
そこで住所という数字を割り振ってもらう作業が「表示登記」という作業になります。




この表示登記は売主・不動産仲介会社では行えず、土地家屋調査士が行います
表示登記の費用は基本的に買主負担で、この作業は約1週間程度の期間を要します。この表示登記を行い、新築分譲住宅に住所が付いて初めて、購入できる状態になります。
② 住所移転の手続き
表示登記が完了したら、次に住所移転を行います。ここで実際に起こりうる話をします。行政窓口に住所を移転しに行くと、「もうその住所に居住していますか?」と聞かれることがあります。




ここでひるんではいけません。まだ決済・引き渡しを受けていませんが、「はい、この住所に居住しています」と言わないとダメなんです
なぜこんなことをするかというと、所有権移転登記・抵当権設定登記の住所を新住所にするためです。旧住所で登記した場合、いずれ住所変更が必要になり、余計な費用がかかってしまいます。
③ 住宅ローンの本審査と金銭消費貸借契約と決済・引渡し
売買契約後すぐに本審査(正式審査)、本審査承認後は住宅ローンを借りるための金銭消費貸借契約を銀行と金融機関します。




この住宅ローンの金銭消費貸借契約を締結するリミット(期限)は、決済・引渡しをする日の4~5営業日前までになります
そして最終的に、金融機関で住宅ローンを実行し、売主に残代金を支払い、物件の引渡しを受けます。
それまでにも購入した物件の「立会い」もありますし、考えることも火災保険や団信の内容や追加工事・オプションの検討など、やらないといけないことはたくさんあります。
こんな感じで1ヶ月ルールの中で引き渡しまでは思っている以上に忙しくなります。
なぜ1ヶ月ルールが存在するのか




ていうか、なんでそんなに急かすん?
それではなんでこの建売新築一戸建ての取引で「1ヶ月ルール」というものがあるのでしょうか。
これには主に2つの理由があります。
- 低価格を実現するために資金の回転を早くしている
- 物件の売買契約が解除された時のリスクの最小化
① 資金の回転を早くして低価格を実現
1ヶ月ルールを作ってできるだけ早く引き渡しを終えようとするメインの理由は、建売の特徴でもあるリーズナブルな価格帯を実現するために資金の回転を早くしたいからです。




建売ハウスメーカーは会社のお金を使って、土地を買い・建物を建ててそれを販売して利益を上げますが、資金の回転を早くすることが重要なんです
資金にも限りがあるので、1件の建売を作ることができる資金があっても、そのお金で1年間で3回建売を販売するのと、4回建売を販売するのとでは利益が違います。
② 飯田グループなど大手の資金回転戦略
特に飯田グループやケイアイスター不動産などの大手は、一般的な不動産会社と違い、同じ資金を年に2回転以上させることを目標にしています。




それ、すごい忙しそうやな。。。
時間をかけていると経費がかかってしまいます。ローコスト住宅を実現するために、手続きを完全にシステマチックにしています。
地元系の分譲会社と飯田グループ系を比較すると、500万円くらい価格差が生じることもあるという現実は、この資金回転の速さが実現している部分が大きいのです。




「そんな変わる?」って思いますよね。そのおかげで安くなっているんだと思って、厳しい日程についてきていただけるとありがたいです
③ 解除時の機会損失リスクを最小限に抑える目的
1ヶ月ルールのもう一つの理由は、その契約が解除になった時の機会損失の期間を最小限に抑える目的があります。




建売新築一戸建ては「新築」として販売できる期間は完成後1年という広告のルールがあります
もし引き渡しまで何ヶ月も待って、その後解除されてしまうと、「新築としての販売」ができる期間がかなり減ってしまう可能性があるのです。
このリスクを避けるため、「1か月以内に引き渡しを受けられる人にしか販売しない」というルールになっているわけです。これもある意味、低価格で販売できるようにするためのリスク管理といえます。
1ヶ月ルールのあるある話
最後に不動産仲介業者としての1ヶ月ルールあるあるを紹介していきます。
① 価格交渉などをするともっと期間短縮されることも
新築一戸建て建売住宅の購入というと価格など条件交渉をする方もいます。こういった交渉をすると、「交渉の条件を了解する代わりに日程をこの日程でお願いします」、というような感じ建売ハウスメーカーさんが言ってくる場合があります。




もともと「1ヶ月ルール」でタイトな日程だったものがより厳しくなります
12日とか月の中ごろに契約をする話でも「月内引き渡しでお願いします」というような話も普通にありますので、この日程で動くしか無理、1日でもズレたら末日までに決済できないというようなスケジュールの場合も時々あります。
そんなことがあるので月末の銀行は不動産取引する人たちで混むんです。
② 期間が延長されると本当に嫌な雰囲気になる
売買契約時に決めた引渡しまでの期間、1か月がどうしても無理な場合は「期間延長同意書」で期間を延ばすと言いましたが、これをすると本当に嫌な雰囲気になります。




そんなにヤバいんか。。怖っ。。
売主の担当者はそれぞれ直属の上司に「なんでそうなったん?」的な詰問を受けますので嫌な雰囲気になりますし、その詰問を受けた担当者と仲介業者の空気感も「何してくれてるんですか」的な雰囲気になります。
これがまた絶妙に、お客様が事故に遭われて、、、とかそういった本当のアクシデントとかなら大丈夫なのですが、よくある「買主が書類を集め忘れてて」とか「銀行の保証会社が混んでて伸びた」とかそんな感じの話であれば、ほとんどの場合、仲介業者の責任になります。




仲介業者と売主担当者間で本当に気まずい雰囲気になります
引き渡し期日を守れなかった買主側が全部悪い、となります(あたりまえと言えばあたりまえですが)。
③ ルール自体の期間が短縮されたりする
こんな建売住宅販売の「1ヶ月ルール」ですが、このルール自体が1ヶ月から減ったりします。25日ルールとか。。。




ルール変わったんですよね… どころではなく、買主・仲介業者はその5日短縮はめっちゃ大変なんです
これは建売ハウスメーカー周辺でよくある話で、工事業者の納期とかでもよく聞きます。1日減らされてすごい大変なことなってて…とかよく聞きます。
合理化・期間短縮は建売ハウスメーカーには至上命題なわけです。
④ 短期間取引の評価
厳しいことばかり言っていると建売ハウスメーカーさんに悪いので良いこともいうと、今でもすごい短期間で引き渡しまでたどりつけた取引のことを覚えててくれます。




「あの時の鈴木さんの取引はすごく助かりました。お客さんにもご迷惑をおかけしたけど、あれはすごかったです」って今でもことあるごとに言ってくれたりします
それくらい期間の短縮に全力を注いでいるのが建売ハウスメーカーさんです。基本的にはそんな非人道的な日程になることはないですが、1ヶ月ルールの中で契約から引き渡しまで頑張っていきましょう。
契約書の中で「引き渡し日」というところはきちんと確認してください。あとで日程トラブルにならないように。
ネット銀行を使いたい(1ヶ月ルールに対応するための方法)




どうすれば1ヶ月ルールに上手く対応できるん?
特に手続きに1ヶ月以上かかるネット銀行などの住宅ローンを利用したい場合、どうすればよいのでしょうか。
① 事前に住宅ローンの審査を済ませておく
ネット銀行を使いたいなら、契約前までにネットで事前審査を済ませておくことが大切です。




事前審査が通れば本申込手続きのご案内の書類が送られてきます。案内に、本審査で必要な書類が記載されていますので、その書類を予め取り寄せて用意しておきます
- 身分証明書(運転免許証など)
- 健康保険証
- 源泉徴収票
- 所得証明書(課税証明書など)
- 住民票
タイムリミットが4週間となると1日のロスでも惜しいため、以下の点を心がけましょう。
- 予め事前審査を終わらせておく
- 必要書類を準備しておく
- 契約したら次の日にでも本申込をできる体制を整えておく
② 銀行への期日の伝達
もう一つ大切なことは、ネット銀行へ本申込をするときに「ローン特約の期日と残金決済の期日に間に合わせて欲しい」という旨を強調して伝えておくことです。




例えば「ぜひ、期日まで間に合わせて欲しい。もし、間に合わなければ、他の銀行に申込みせざるを得ない」くらいなことを伝えると、優先して手続きをしてくれるのか、間に合うことが多いようです
③ 別プランも準備しておく
間に合わなかった場合のことも考えて、間に合う可能性が高い銀行にも申込みしておく事が大切です。




三菱UFJ銀行やりそな銀行などは、ネット銀行と比べても遜色ないくらい低金利で、比較的手続きが早いので、別プランで準備しておいて損はありません
受験でいうと「第1志望:ネット銀行、第2志望:りそな銀行」という感じで同時並行で申込みするといいです。




同時並行で申込みしても大丈夫なん?
大丈夫です。
もし両方から合格通知がきたら、残金決済の期日までに間に合うほうで進めれば良いのです。
④ どうしても無理な時の交渉方法
そんな1ヶ月ルールですが、どうしても無理な場合もあるにはあります。
基本的には契約書を作る段階で完全に無理ではない日程を作っているのですが、途中でアクシンデントがあって日程が1週間伸びてしまうなどなどごく稀に出てきます。
そんな時は「期間の延長同意書」というような売買契約の内容はそのままに引き渡しの期間だけ伸ばす書類を作ることになります。




かといって「どうせ延長できるんでしょ?」みたいなテンションはダメですよ
売買契約を締結したときには「その日に引き渡しを受けます」という約束をしたのと同じ意味になります。
歯医者や美容室の予約をリスケするテンションでリスケはしないでください。
年末年始やゴールデンウイークなど、連休を挟むと金融機関が休みになるため実務上絶対に間に合わない場合は、1週間程度延ばしてもらえる可能性はあります。
また、住宅ローンの手続きの事情を説明すると、1ヶ月(30日)程度に延長してもらえることもあります。
ただし、3月や9月など売主の決算月になると、譲歩してもらえることはまずないので注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
建売新築一戸建ての「1ヶ月ルール」について解説してきました。要点をまとめると、
- 建売新築購入では契約から引渡しまで1ヶ月以内というルールが一般的
- 特に飯田グループ系やケイアイスター不動産では3~4週間以内とさらに短い
- この短期間で住宅ローン審査や表示登記、住所移転などの手続きをすべて完了させる必要がある
- 1ヶ月ルールの理由は資金回転を早くして低価格を実現するためと解約リスクの最小化
- 対応するには事前審査を早めに済ませる、必要書類を準備しておく、複数の銀行に申込むなどの戦略が有効
建売新築一戸建ての購入を検討している方は、この「1ヶ月ルール」を理解し、前もって準備をしておくことで、慌ただしい日程の中でも落ち着いて手続きを進めることができるでしょう。




契約書の中で「引き渡し日」というところはきちんと確認してください。後で日程トラブルにならないように
購入検討者としては、「多少価格が高くてもゆっくり手続きをしたい」のか、「手続きが忙しくても少しでも安い方が良い」のか、自分の優先順位を考えて選択することが大切です。