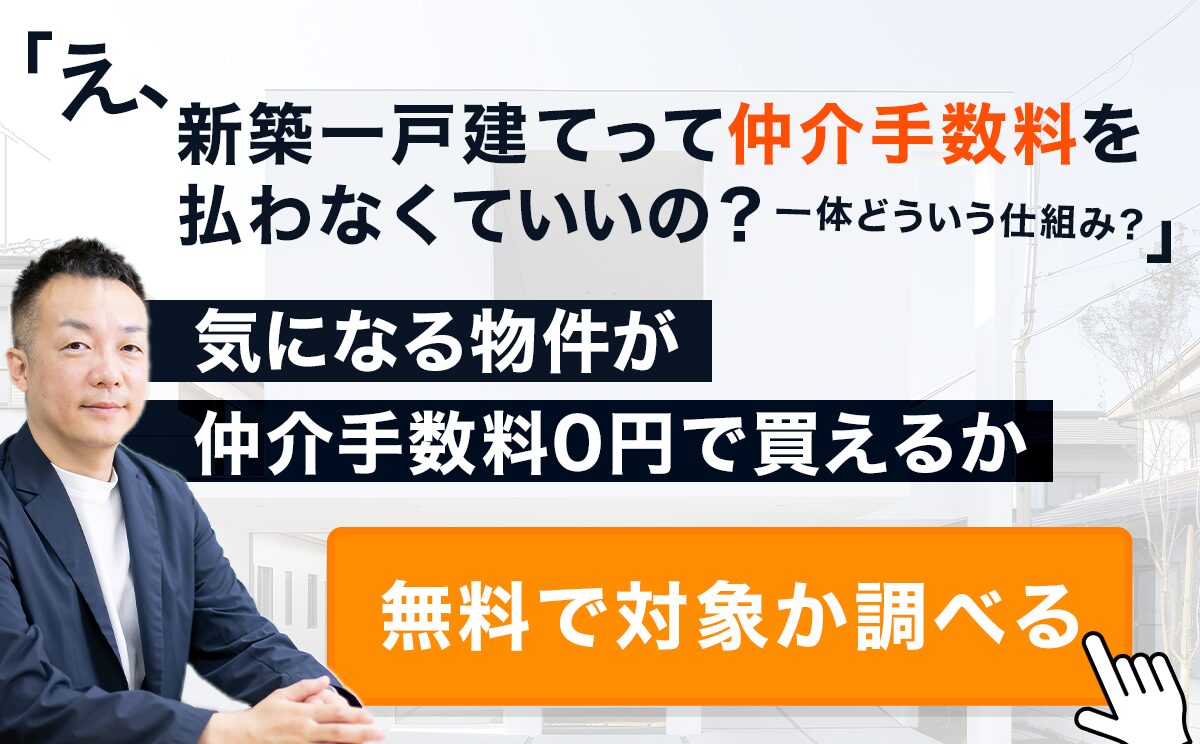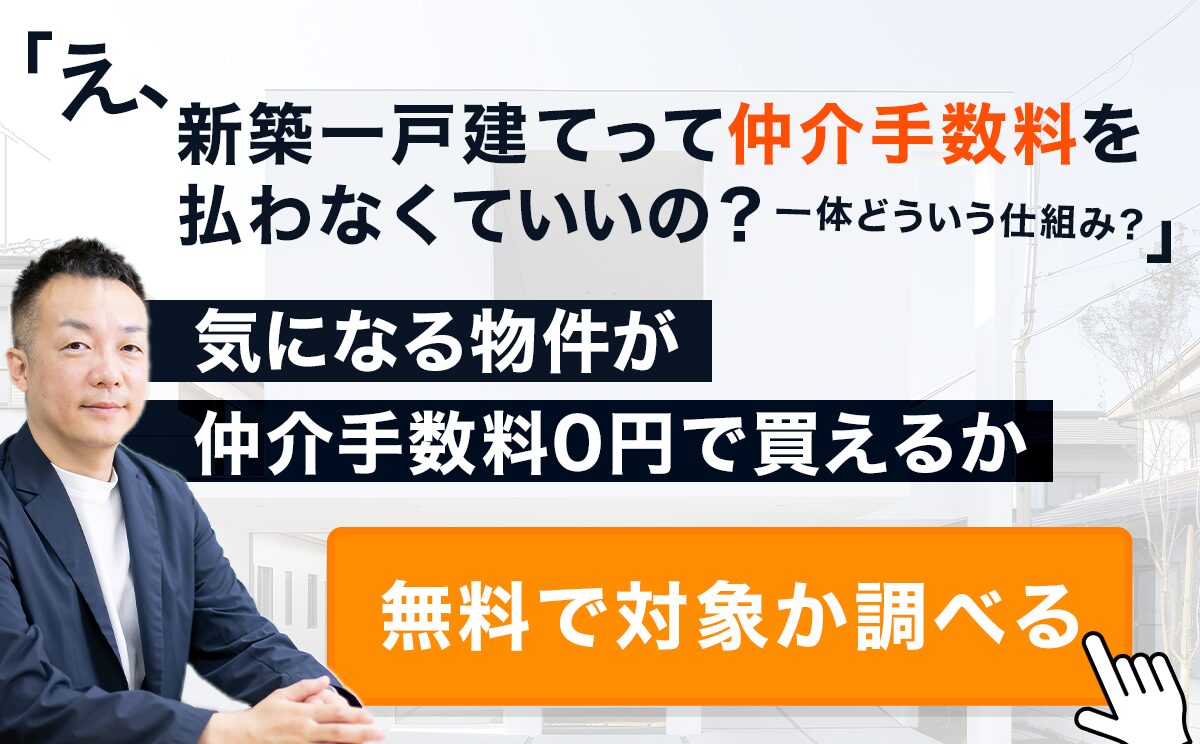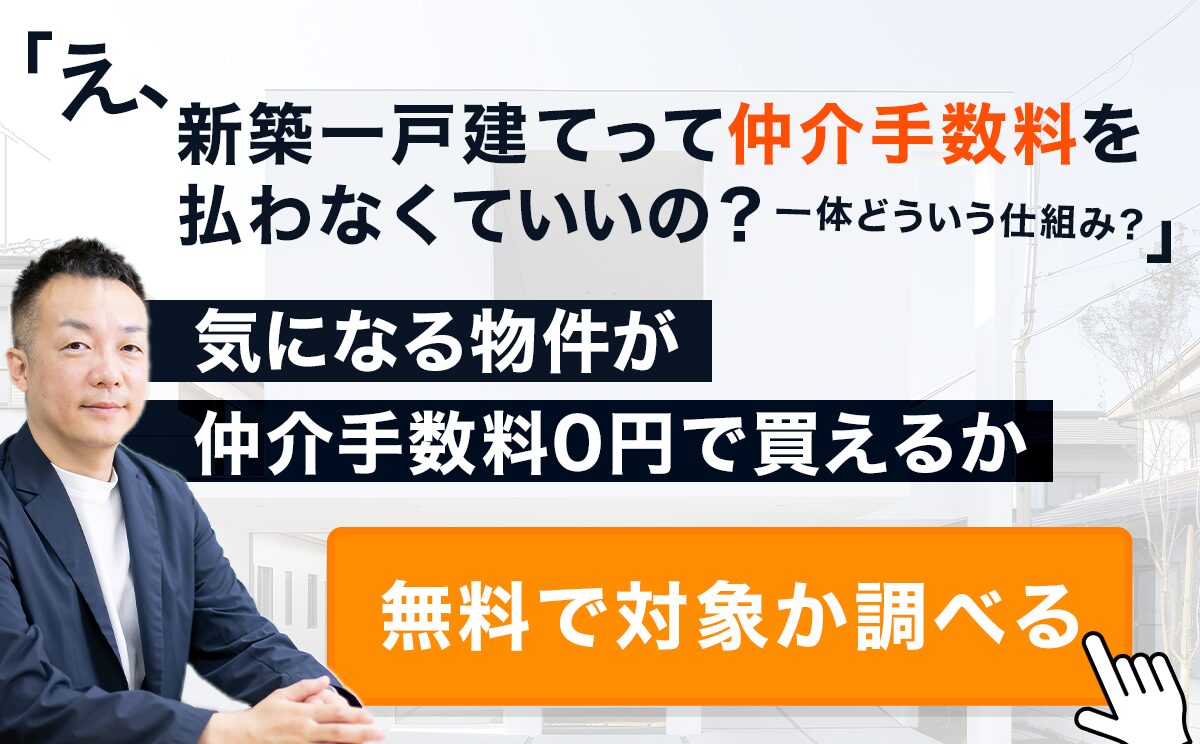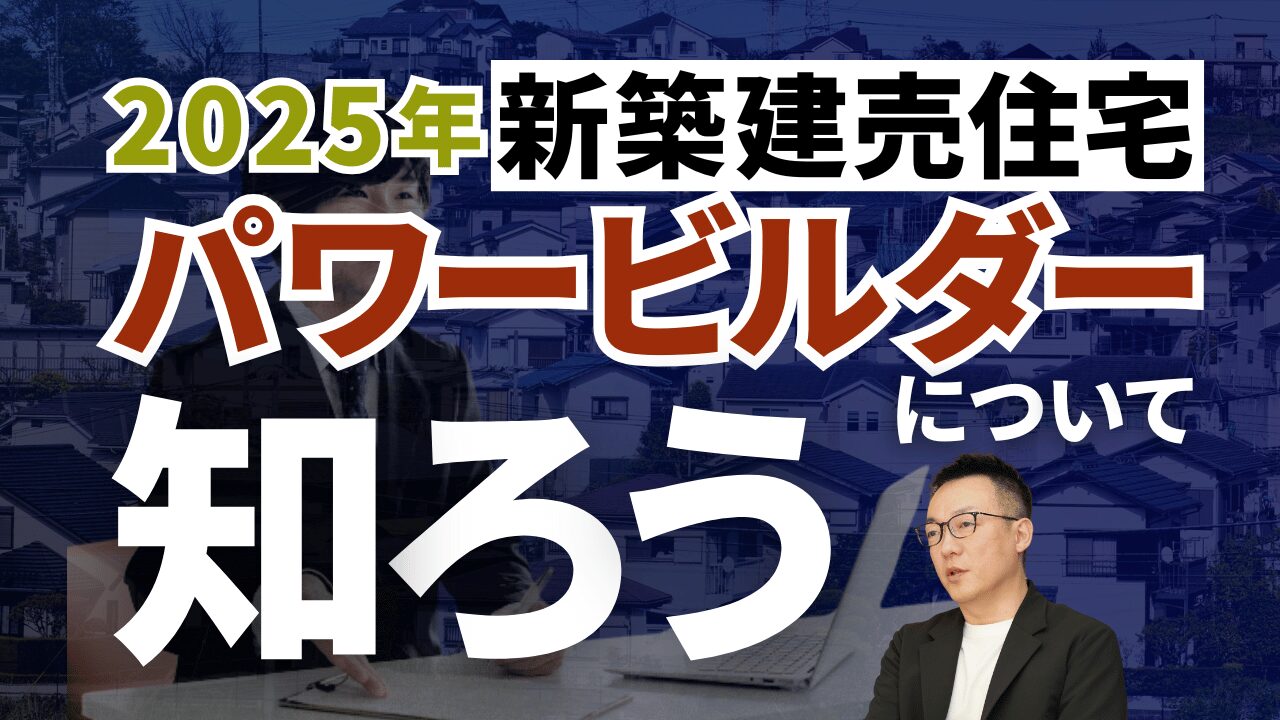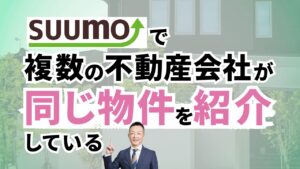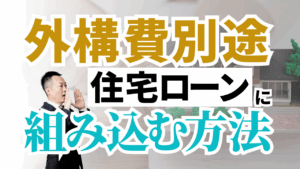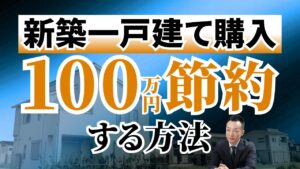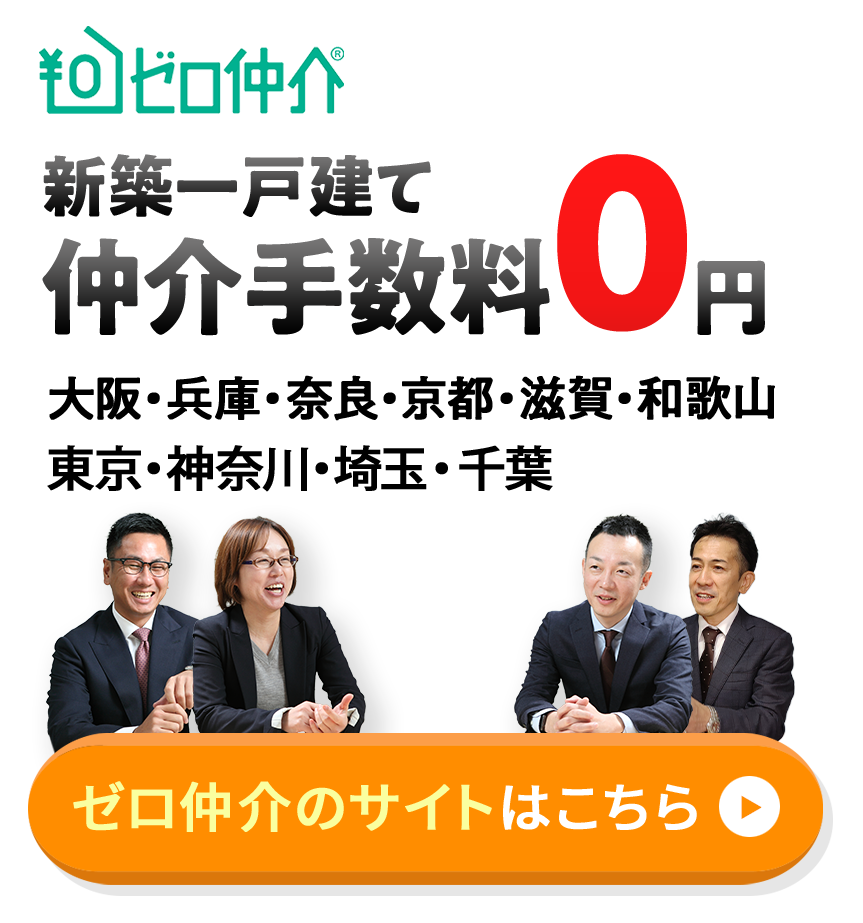こんにちは。ゼロ仲介の鈴木です。
 ヒガシノさん
ヒガシノさん新築一戸建て欲しいけど、今は住宅価格が高騰してるって聞くし…




パワービルダーの建売住宅って実際どうなん?




値段が上がり続けるなら今買うべき?それとも様子見?
なんて悩んでいませんか?
実は、パワービルダーの動向を知ることで、最適な住宅購入のタイミングが見えてきます。
この記事では、新築建売住宅市場の現状と、パワービルダー各社の最新動向を徹底解説します。
パワービルダーとは何か?
まずは「パワービルダー」という言葉の意味から解説します。。




パワービルダーとは、低価格帯の戸建て住宅を大量に供給する住宅メーカーのことです
パワービルダーは大規模な土地開発から、規格化された住宅の建設、販売までを一貫して手がけています。




ほんまに「パワー」あるんやね!量産型の家メーカーってことやな!
その通りです。効率化された建築プロセスにより、注文住宅と比べて手頃な価格で新築一戸建てが手に入るのが最大の特徴です。
一般的に、パワービルダー系の住宅は「仲介物件」という形で、仲介会社に販売を任せるビジネスモデルを展開しています。
日本の新築建売住宅市場で最大のシェアを誇るのは「飯田グループ」です。
アーネストワン、一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、アイディホームの6社が経営統合したグループで、新築建売住宅購入者の3人に1人は飯田グループ系の建売住宅を購入しているというほど、シェア率が高いんです。
その他の主要企業には、ファースト住建やメルディアDCなどがあります。




知らんかった。3人に1人が飯田グループの家に住んでるって、めっちゃ影響力あるやん!
そうなんです。
大手パワービルダーの建売住宅は、長年の実績と豊富な建築ノウハウによる品質の安定性が強みです。
また、多くの施工実績があるため、アフターサービス体制も整っており、購入後の安心感につながります。
現在の建売住宅市場の状況
1.住宅価格高騰の要因
2020年以降、新築戸建ての価格は上昇し続けています。




SUUMOリサーチセンターの調査によると、2023年の首都圏新築一戸建ての平均購入価格は4,515万円となり、調査開始以来の最高額を記録しました




めちゃ高い!
この価格上昇の主な要因は以下の3つです。
- 建築資材や住宅設備の値上がり:「ウッドショック」やウクライナ情勢による建築資材不足、運搬コストの高騰が影響しています。建築資材は過去3年間で約30%上昇しています。
- 人件費の高騰:働き方改革を背景にした職人の人手不足により、人件費が大幅に上昇しています。
- 地価の上昇:特に都心部では地価が継続的に上昇しています。




えげつないな~。4,500万円超えてもうてるんか…でも資材高騰とか職人さん不足とか、仕方ない面もあるんやな
価格上昇が続く今だからこそ、早めに購入を決断することで将来的な値上がりを回避できる可能性があります。
また、現在の建売住宅は省エネ性能も向上しており、長期的には光熱費削減につながり、資産価値も維持しやすくなっています。
2.パワービルダー各社の業績悪化
住宅価格の上昇にもかかわらず、パワービルダー各社は業績悪化に直面しています。




飯田グループホールディングスは2024年3月期の連結最終利益を当初予想の700億円から300億円に55.7%下方修正しました
飯田グループの決算資料によると、売上はわずかな減収ながら、営業利益は43.9%減、純利益は53%減と利益面では大幅な減益となっています。
この業績悪化の主な要因は、原価の高騰を販売価格に転嫁できていないことです。
1戸あたりの原価が36万円増加したにもかかわらず、販売単価は17万円下落という状況に陥っています。




ほんま?値上げせずに利益減らしてるってことは、売れんかったら値引きするって考えてもいいんかな?
その通りです。
このような状況は、購入者にとってはむしろチャンスかもしれません。
各社が在庫を抱え、価格調整を行っているため、タイミングによっては予想以上に好条件で購入できる可能性があります。
特に完成在庫の早期販売を目指している物件では、大幅な価格引き下げが行われているケースもあります。
3.都心部と郊外の需要格差
住宅市場では、都心部と郊外で明確な需要格差が生じています。




特に郊外での販売不振が深刻化しており、埼玉では大宮より北、東京では武蔵小金井駅より西側など、都心から離れた地域では売れにくい状況が続いています
一方、都心部では高級路線の戸建てにシフトする動きも見られます。
東京の高級住宅地では、1億5000万円を超える2億円、3億円という超高級建売住宅も登場しています。




ふぁ!?3億円の建売住宅!?お金持ちはどこにでもいるんやねぇ
この需要格差は、郊外の建売住宅がコストパフォーマンスに優れたチャンス物件になる可能性を示唆しています。
都心へのアクセスを考慮しつつも、少し郊外に目を向けると、同じ予算でより広い土地や充実した設備の住宅を手に入れられるかもしれません。
特に在宅勤務が普及した現代では、毎日の通勤距離よりも住環境の質を優先する選択も十分考えられます。
パワービルダー各社の戦略と動向
パワービルダー各社は厳しい市場環境の中で、様々な生き残り策を模索しています。




飯田グループは2013年に6社の経営統合を行い、市場での競争力を高めています。各社がエリアごとに役割分担し、経営資源を効率的に活用しています。これは効率化の流れですね
そして日本市場の飽和を見据えて、海外進出も積極的に進めています。
飯田産業はロシアに、アーネストワンは中国やアメリカ、東南アジアに、東栄住宅はフィリピンに進出するなど、体力のあるハウスメーカーは海外での収益確保に動いています。
このような大手グループの戦略的統合は、消費者にとっては品質と価格のバランスが取れた住宅の供給が期待できることを意味します。
一方、ファースト住建は、飯田グループからの経営統合の誘いを断り、独自の道を歩んでいます。




ちょっと、ごちゃごちゃしてきたわ,,,要は大手は合併して効率化したり、海外に出たりして、生き残りをかけてるってこと?
その通りです。
また、注目すべきは、オープンハウスによるメルディアDCの買収も業界内で話題となりました。
両社はビジネスモデルが大きく異なり、メルディアDCは「仲介物件」モデル、オープンハウスは「自社売り」モデルを採用しています。
このような業界再編は、各社のサービスの差別化や品質向上につながる可能性があります。
市場が厳しさを増す中、一部のビルダーは高級路線へのシフトを図っています。




特に都心部では「突き抜けた高い価格設定」で市場に新築供給する会社が増えています。この傾向は、中価格帯の建売住宅においても品質向上につながる好影響をもたらす可能性があります
高級路線で培った技術やデザイン性が一般の建売住宅にも波及し、住宅全体の品質が底上げされるでしょう。
今後の住宅市場の見通し
1.住宅価格の今後の予測
専門家によれば、住宅価格が下がる要素は当面見当たらないとされています。




原油高の継続、運搬費の高騰、そして世界的な脱炭素の取り組みの加速など、様々な要因が価格上昇に影響しています
特に注目すべきは、2025年4月以降に全ての建築物に「省エネ基準」への適合が義務付けられる点です。
断熱等級4、一次エネルギー消費量等級4以上を満たすことが必要になり、これに伴う建築コストの上昇は避けられない見通しです。




え!?省エネ基準が義務化されるんか!それって家が高くなるってこと?
その通りです。
ただし、省エネ基準が引き上げられることで住宅の品質が向上し、長期的には価値が下がりにくい住宅が増えるという側面もあります。
この観点からすると、今のタイミングでの新築建売住宅の購入は将来的な価格上昇を回避する賢明な選択になり得ます。
特に2025年の省エネ基準義務化前の最後の機会として、比較的コストパフォーマンスの良い住宅を手に入れるチャンスと言えるでしょう。
2.限られた予算で家を建てる方法
住宅価格が高騰する中でも、限られた予算内で家を建てるための方法としては、以下のような選択肢があります。
- エリアを変える:駅や商業施設から少し離れた場所を選び、土地代を抑える。
- 床面積を小さくする:コンパクトな住宅にすることで、基礎工事や屋根工事の費用を抑えられる。
- ローコスト住宅が得意な会社を選ぶ:間取りをパターン化したり、設備仕様を絞った会社を選ぶ。
- 建売住宅の購入を検討する:注文住宅と比べると価格が抑えられる建売住宅を検討する。




建売住宅の最大のメリットは、実際に完成した状態を見て購入判断ができることです。「百聞は一見にしかず」のとおり、図面や3Dモデルではなく実際の空間を体感できる安心感があります
また、引き渡し後すぐに入居できる点も大きな魅力です。
注文住宅では設計から完成まで時間がかかりますが、建売住宅ならその待ち時間を大幅に短縮できます。




たしかに、実際に見て決められるのは大きいな。「思ってたんと違う!」っていうリスクが減るもんな
3.購入タイミングの考え方
「住宅価格が高騰しているので、様子を見るべきか」という疑問に対して、専門家は「ライフステージを考慮して決断すべき」とアドバイスしています。




価格の様子を見ているうちに、家を建てるベストなタイミングを逃してしまうリスクもあります
例えば、子ども部屋がある広いリビングの家を建てても、子どもはその部屋を数年しか使わずに家を出てしまう可能性があります。
不景気になれば住宅価格が下がるかもしれませんが、同時に給与やボーナスも減少する可能性があり、購入自体が難しくなるかもしれません。
専門家は「住宅は利用価値を重視するべきで、資産価値は付随的でよい」という考え方を示しています。




なるほどー。「価格が下がるまで待とう」ってばっかり考えてたら、いつまでたっても買われへんってことやな?
その通りです。新築一戸建ての持つ「新しいスタート」の象徴としての価値も見逃せません。
家族の記念日や子どもの成長、季節の変化など、様々な思い出が積み重なっていく舞台として、新築住宅には特別な意味があります。
誰も住んだことのない空間で、自分たち家族だけの歴史を刻んでいく喜びは、建売住宅購入の大きな魅力の一つです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
パワービルダーを中心とした新築建売住宅市場は、厳しい状況に直面していますが、このような市場環境だからこそ、消費者にとっては新築建売住宅を購入する好機と捉えることができます。
価格上昇が続く中、今購入することで将来的な値上がりを回避できる可能性があります。
在庫調整のためにお得な価格設定になっている物件もあり、理想の住まいを予算内で手に入れられるチャンスです。
新築建売住宅を購入する際に特に注目したいのが、仲介手数料の節約です。
通常、新築一戸建て購入時には物件価格の約3%(約100万円)の仲介手数料がかかりますが、「ゼロ仲介」のようなサービスを利用すれば、仲介手数料が0円で住宅購入が可能になります。




例えば4,000万円の物件だと、仲介手数料だけで約120万円も節約できるんです
また、新築一戸建て購入では、物件選びだけでなく住宅ローンの選択も重要です。
適切な金融機関と借入プランを選ぶことで、総支払額が100万円程度変わる可能性もあります。
さらに、物件価格の交渉サポートを受けることで、購入費用全体の最適化が図れます。




ほんまに!?100万円って大きいな。そんなサービスあるんや
そうなんです。住宅購入を検討している方は、価格の様子見よりも、自身のライフステージを重視した判断が重要です。
そして、その判断をサポートしてくれる信頼できるパートナーを見つけることも成功の鍵です。
透明性の高い費用明細の提示、LINEを活用した気軽な相談体制、物件情報の視覚化など、顧客中心のサービスを提供している会社を選ぶことで、スムーズな住宅購入が実現します。
新築一戸建て購入をお考えの方は、仲介手数料0円で充実したサポートを受けられる「ゼロ仲介」の公式サイト【https://zero-chukai.com/】をぜひチェックしてみてください。
住宅は単なる資産ではなく、家族が快適に暮らすための場所です。
かしこい選択で、理想の住まいをお得に手に入れましょう。