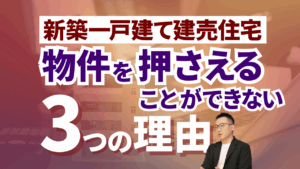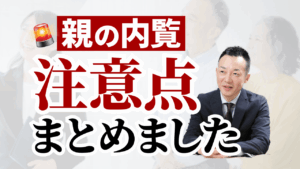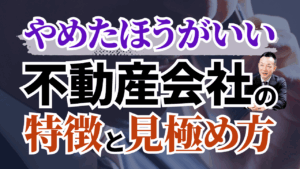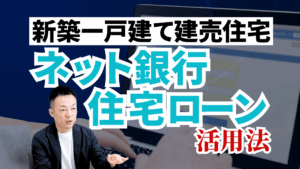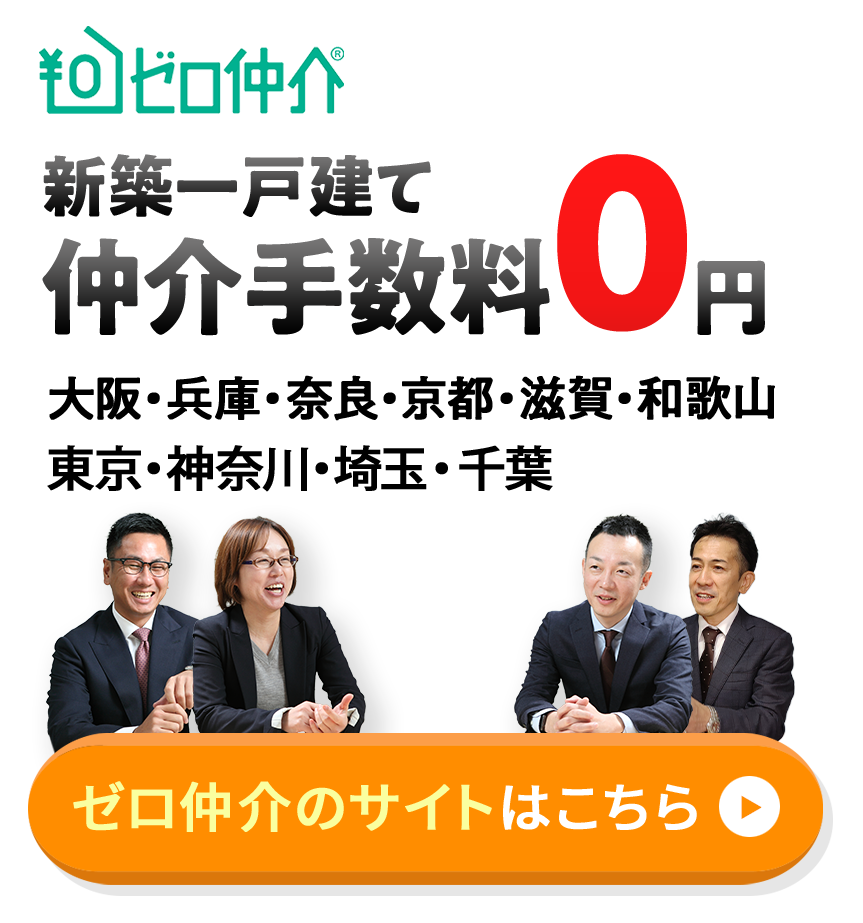こんにちは、ゼロ仲介の鈴木です。
 ヒガシノさん
ヒガシノさんこの地域って水害とか大丈夫なんかな?




新築一戸建てを買いたいけど、災害リスクが心配
なんて思っていませんか?
実は、ハザードマップを使えば、新築一戸建て建売住宅購入前に災害リスクをしっかり確認できるんです。
この記事では、新築一戸建て建売住宅を検討している方に向けて、ハザードマップの基本から入手方法、活用法まで徹底解説します!
ハザードマップとは
近年、日本各地で「数十年に一度」「数百年に一度」と言われる大規模災害が毎年のように発生しています。




2020年8月28日からは宅建業法の改正により、不動産取引時に不動産事業者がハザードマップを提示して水害リスクを説明することが義務付けられました
ハザードマップとは「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所などを表示した地図」のことです。
防災マップや被害予測図、被害想定図などとも呼ばれています。




ハザードマップって、なんか難しそうやなぁ…住宅買うときに見る必要あるん?




必要あるどころか、、、絶対に見てください
新築一戸建て建売住宅購入時に確認すべき災害リスク情報はこの4つです。
| 浸水予想区域 | 河川氾濫や大雨による浸水の深さや範囲 |
| 土砂災害リスク | 土石流やがけ崩れなどの危険性がある区域 |
| 津波・高潮リスク | 海岸部での津波や高潮による浸水範囲 |
| 地震被害 | 想定される震度や液状化リスク |
日本は地震や水害といった災害が起こりやすい国土です。2011年の「東日本大震災」や2020年の「令和2年7月豪雨」など、甚大な被害をもたらした災害がありました。
これらの被害が集中した地域の多くは、実はハザードマップでリスクが公表されていたエリアであったことが多いのです。
ハザードマップの入手方法
ハザードマップを入手する方法は大きく分けて2つあります。




ハザードマップの入手方法を知ることは、めちゃ大事です。まずは入手方法をざっくり説明します
1.市区町村で作成しているハザードマップを閲覧する
一つ目は、地方自治体が作成しているハザードマップです。
これは役所に行けば手に入れることができますし、多くの自治体では公式ウェブサイトでも公開しています。
インターネットで「地域名 ハザードマップ」と検索すれば、該当地域のハザードマップに関する情報が見つかります。
多くの場合、PDFファイルで提供されているので、印刷してじっくり検討することも可能です。




ネットで検索したらすぐ見られるんか!でも、いろんな災害があるから、どのハザードマップを見ればええんやろ?




それなら、次の方法がおすすめです。各自治体のマップを比較するなら、国土交通省のポータルサイトが便利ですよ
2.国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」で閲覧する
もう一つは、国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」を利用する方法です。
このウェブサイトでは、全国のハザードマップを閲覧することができます。
国土交通省のハザードマップポータルサイトでは、主に「わがまちハザードマップ」と「重ねるハザードマップ」という2種類のサービスを提供しています。
わがまちハザードマップ
「わがまちハザードマップ」は、各自治体が作成したハザードマップにリンクが張られています。
都道府県と市区町村名を選択するだけで、全国のハザードマップを閲覧できます。
このサービスで閲覧できるのは以下のようなハザードマップです。
- 洪水ハザードマップ
- 内水ハザードマップ
- ため池ハザードマップ
- 高潮ハザードマップ
- 津波ハザードマップ
- 土砂災害ハザードマップ
- 地震防災・危険度マップ情報
重ねるハザードマップ
「重ねるハザードマップ」は、より詳細な分析が可能なツールです。
市区町村名などを入力すると該当地域の地図が表示され、「洪水」「土砂災害」「高潮」「津波」などの災害情報を地図上に重ねて表示できます。




「重ねるハザードマップ」の最大の特徴は、複数の災害リスクを同時に確認できる点です
たとえば、検討している新築一戸建て建売住宅の分譲地について、洪水リスクと土砂災害リスクを同時に確認することができます。
新築一戸建て建売住宅を選ぶ際のハザードマップの見方と活用法
ハザードマップを活用する際のポイントは、色分けや記号の意味を正確に理解することです。
一般的に、色が濃くなるほど危険度が高いことを示しています。
各色がどの程度の災害を想定しているかは、ページ内の「解説凡例」でしっかり確認しましょう。




ゼロ仲介では、物件提案時にあらかじめハザードマップを確認いただけるオリジナルツールを使っております




ハザードマップを事前に確認できるのはめちゃいいな
建売住宅の分譲地や物件エリアをハザードマップで確認する基本的な手順は以下の通りです。
- 検討している新築一戸建て建売住宅の住所を確認する
- 国土交通省ハザードマップポータルサイトにアクセスする
- 「重ねるハザードマップ」で住所を入力する
- 土地の災害リスク(洪水、土砂災害など)を確認する
- 必要に応じて「わがまちハザードマップ」で詳細情報を確認する
また、不動産情報サイトの中には、物件検索と同時にハザードマップ情報を表示できる機能を備えているものもあります。
例えば、LIFULL HOME’Sの「地図から探す」機能では、物件を探しながら洪水ハザードマップを重ねて表示することができます。
浸水想定エリアにある新築一戸建て建売住宅を検討する場合の判断基準
ハザードマップで調べると、特に都市部では浸水想定エリアに含まれる土地が多いことがわかります。




大阪府の多くのエリアが浸水想定区域に入っています
大阪市内や堺市・高槻市・茨木市などでは広い範囲が浸水想定エリアになっています。




住みたい街でよく名前が上がる西宮や吹田、千里中央あたりも結構色がついてるな。新築一戸建てを建てる会社は、ハザードマップ見てないん?




見ていないという訳ではないのですが…実はほとんどの売主は、ハザードマップで浸水想定区域であっても土地を仕入れて分譲しています
あくまでも、利便性と収益性のみで分譲地を選定しているのが現状です。
建売住宅を検討する際、理想的には浸水リスクの低い場所を選ぶことが望ましいですが、現実には利便性の高いエリアほど浸水想定区域に入っていることが多いのが実情です。
もし検討している建売住宅が浸水想定エリアにある場合、以下のポイントを確認することが重要です。
1.浸水の深さと新築一戸建て建売住宅の建築仕様の関係
浸水想定エリアでの建売住宅選びで最も重要なのは、想定される浸水の深さと建物の構造の関係を理解することです。
例えば、浸水想定が50cm程度であれば、現在の一般的な新築一戸建て建売住宅では床上浸水する可能性は比較的低いと言えます。
これは、現代の建売住宅では基礎高が40cm以上あり、宅盤(地盤)から床までの高さは50cm以上あるためです。
さらに、宅盤は道路よりも10〜15cm高くなっているのが一般的です。
つまり、道路から床上までの高さはおおよそ60cm程度になるため、浸水想定が50cmのエリアであれば、床上浸水のリスクは比較的低いと判断できます。




浸水想定50㎝未満であれば、大丈夫ということか
2.新築一戸建て建売住宅の標準的な基礎高とリスク評価
建売住宅を実際に見学する際には、以下の点をよく確認しましょう。
- 宅盤(地盤)が道路面よりも10cm以上高くなっているか
- 基礎の高さが宅盤から40cm以上あるか
- 道路から床面までの総合的な高さはどれくらいか




これらの条件を満たしていれば、浸水想定が0〜50cm程度のエリアでは、床上浸水の可能性は低いと考えられます
3.注意すべき新築一戸建て建売住宅の特徴
一方で、特に注意が必要なのは以下のような新築一戸建て建売住宅です。
- 半地下形状の基礎仕様になっている物件
- 道路と宅盤の高さが同じか、差が少ない物件
- 基礎の立ち上がり部分が極端に低い物件




特に大阪市内や神戸市の都心部にある狭小住宅や3階建ての物件は注意が必要です
高さ制限などの建築規制を回避するために、半地下形状の基礎仕様で建築している物件があります。
このような物件では、ちょっと道路冠水しただけですぐに床上浸水する可能性があります。
どうしても、そのような物件を購入するという場合は、火災保険の水災オプションに入ることは必須です。
水災オプションに入れば、万一、床上浸水になった場合でも、修理費用が保険金としておりますので金銭面で心強いです。
新築一戸建て建売住宅購入時の災害リスク対策
ハザードマップでリスクを確認した後は、適切な対策を検討することが重要です。




浸水想定の深さによって、対応方法が異なります。これは本当に覚えておいてください
1.浸水想定の深さ別の対応方法
浸水想定エリアにある建売住宅を購入する際には、浸水の深さに応じた備えが必要です:
| 浸水想定0〜50cm | 標準的な基礎高を持つ建売住宅であれば床上浸水の可能性は低いですが、火災保険の水災補償は検討すべきです |
| 浸水想定0.5m〜3m | 万一の際は1階がほぼ浸水する可能性があります。災害時には「垂直避難」(2階以上への避難)が必要です |
| 浸水想定3m以上 | 万一の際には2階部分も浸水する可能性があります。台風接近時には避難所への「水平避難」が必要です |




地域の避難所や防災も大切よね




今後は、地球温暖化の影響で、自然災害が増加することが予測されています。住宅を購入する時には、利便性だけでなく、災害リスクを考慮する必要があります
新築一戸建て建売住宅選びでの災害リスクと利便性のバランス
建売住宅を選ぶ際には、災害リスクと利便性のバランスを取ることが重要です。
実際に国土地理院の人口集中地区の地図とハザードマップを比較すると、洪水リスクに関係なく人口が集中しているエリアが多いことがわかります。
これは、水害リスクよりも利便性を優先する人が多いという現実を表しています。




実際、2018年の台風21号では、関西地方で大きな被害が出ました
大阪湾岸のタワーマンションでは高潮による浸水被害もありました。
このようなエリアのマンションは、しばらく価格が下落しましたが、現在では当時以上の価格に高騰しています。
水害などの自然災害の被害は、数年経つと、みんな記憶から薄れて、水害リスクに関係なく利便性が良い場所は人が集まり不動産価格が高くなります。




まさに『喉元過ぎれば熱さを忘れる』やな
ハザードマップで知るべきなのは、あくまでもリスクの高さです。
事前にリスクを把握することで、災害が起こりそうなときにいち早く行動することができます。
ハザードマップでリスクが表示されているからといって、そこに住んではいけないということではありません。
建売住宅選びでは、その地域のメリットと同時にリスクも知り、適切な対策を講じることが大切です。




ハザードマップの浸水エリア内であっても、例えば子供の学区域で物件を探していたり、昔から住んでいて顔なじみが多く、その場所を離れられないという人は結構多いんですよ
ハザードマップを見ると分かりますが、例えば、尼崎市・西宮市・豊中市などでは、浸水想定エリアでない物件を探すほうが逆に難しいことが分かります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。新築一戸建て建売住宅を購入する際には、ハザードマップを活用して土地の災害リスクを正しく把握することが重要です。
ハザードマップは市区町村のウェブサイトや国土交通省のハザードマップポータルサイトで閲覧できますが、専門的な知識がないと判断が難しい場合もあります。
そこで心強いのが、ゼロ仲介の物件提案です。
ゼロ仲介では、物件の提案時にハザードマップを確認できるようになっています。
これにより、お客様は事前にハザードエリアかどうかわかって物件探しができるため、安心して物件選びを進められます。
特に浸水想定エリアにある新築一戸建て建売住宅を検討する場合は、基礎の高さや構造をしっかりと確認する必要がありますが、ゼロ仲介の宅建士資格を持つスタッフがこれらのポイントを専門的な視点からアドバイスします。
さらに、ゼロ仲介では仲介手数料0円というメリットがあります。
通常、新築一戸建て建売住宅購入時には物件価格の約3%(数百万円規模の物件であれば100万円近く)の仲介手数料がかかりますが、ゼロ仲介ではこの費用が一切かかりません。
住宅ローンの事務手数料も不要で、購入後のアフターサポートも充実しています。
ハザードマップの確認から物件選び、価格交渉、住宅ローンの提案まで、家づくりに関する様々な不安や疑問をLINEで気軽に相談できるのもゼロ仲介の特徴です。
時間を気にせず問い合わせができ、最短5分で返信が得られるため、忙しい方でも安心してご利用いただけます。
住宅購入は人生の中でも大きな決断です。災害リスクを含めた総合的な判断ができるよう、専門知識を持ったプロのサポートを受けることをおすすめします。
安心・安全な住まい選びを実現するために、ぜひゼロ仲介の公式サイトをご覧ください。