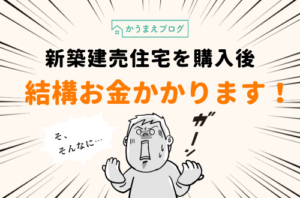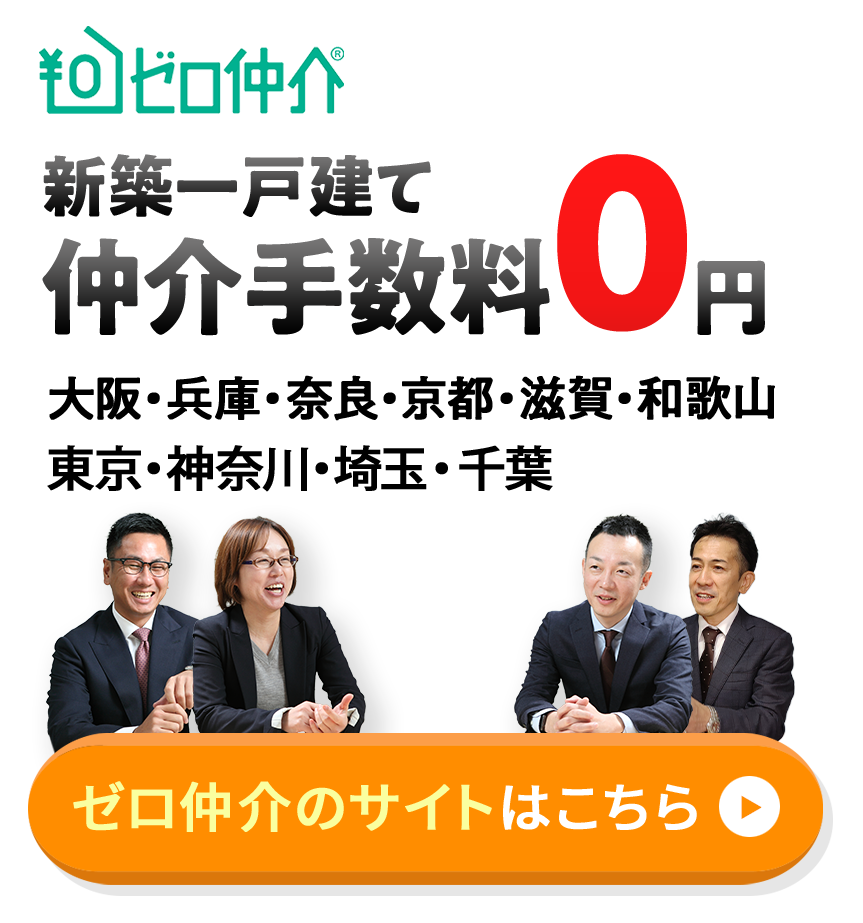こんにちは、ゼロ仲介の鈴木です。
新築一戸建ての購入を検討するとき、多くの方が物件の価格だけに目を向けがちです。
 ヒガシノさん
ヒガシノさん3,000万円の住宅を買うなら、3,000万円用意すればいいんかな?
なんて思っていませんか?
実は、物件価格だけではマイホームは買えないんです。
物件価格以外にも「諸費用」という名目で様々な費用が必要になります。
この記事では、新築一戸建て(建売住宅)を購入する際にかかる諸費用の目安や内訳、支払うタイミング、そして諸費用を少しでも安く抑えるためのポイントまでくわしく解説します。
新築一戸建て建売住宅の諸費用の目安
ざっくりとですが、新築一戸建て建売住宅の諸費用は物件価格の5〜10%程度が目安となります。




一般的な目安としては、「物件価格の5〜10%」が諸費用として必要になるんです
例えば、3,000万円の建売住宅であれば、約150万円〜300万円の諸費用が別途必要になる計算です。




え!?300万円も!?そんなお金どこから出すん?住宅ローンだけで精一杯なんやけど
諸費用の割合に幅があるのは、仲介手数料の有無や金額、住宅ローンの借入条件、火災保険の内容などによって大きく変わるためです。
新築一戸建て建売住宅は土地と建物をセットで購入するため、注文住宅や中古住宅と比較すると諸費用の割合は異なります。
| 建売住宅 | 物件価格の5〜10% |
| 注文住宅(土地から購入する場合) | トータルコストの10〜12% |
| 注文住宅(すでに土地を持っている場合) | 建築費の3〜6% |




建売住宅の諸費用は、その中間程度と考えておけばまちがいありません
諸費用の内訳と詳細
それでは、具体的にどんな費用が必要になるのか、くわしく見ていきましょう。
1.仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社を通して建売住宅を購入する際に発生する費用で、諸費用の中でも最も大きな割合を占めることが多い項目です。
仲介手数料の上限は法律で定められており、以下の計算式で求められます。
仲介手数料の上限 = 物件価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例えば、3,000万円の建売住宅の場合: 3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円 96万円 + 消費税(10%) = 105.6万円




実はこれ、あくまで上限なんです。法律で決められた上限であって、定価ではありません




え?値切れるってこと?
ただし、これはあくまで上限であり、実際の金額は不動産会社によって異なります。
中には、新築一戸建て建売住宅に限り、仲介手数料が無料または半額になるサービスを提供している不動産会社もあります。
また、ハウスメーカーや分譲会社から直接購入する場合(売主物件の場合)は、仲介手数料は発生しません。
購入前に物件が「売主物件」なのか「仲介物件」なのかを確認することも重要です。
2.登記費用
建売住宅を購入すると、所有権の登記や住宅ローンを利用する場合は抵当権の設定などの登記手続きが必要になります。
登記費用の内訳は以下の通りです。
| 建物表示登記(表示登記)費用 | 9万円〜10万円 (土地家屋調査士報酬) |
| 所有権移転登記・保存登記・抵当権設定登記 | 35万円〜40万円 (登録免許税と司法書士報酬) |
合計すると、登記費用は約45万円〜50万円が目安となります。




登録免許税には軽減措置が設けられています。2027年3月31日までの登記であれば軽減税率が適用されるので、今のうちに購入するメリットがあります
例えば、一般住宅の所有権移転登記は通常2.0%ですが、軽減措置により土地は1.5%、建物は0.3%に軽減されます。
3.印紙税
印紙税は、契約書を作成する際に必要な税金で、契約書に収入印紙を貼ることで納めるものです。建売住宅の購入では、主に2つ印紙税が発生します。
- 1.不動産売買契約書の印紙税
-
3,000万円の物件の場合:1万円(2027年3月31日までの軽減措置適用時)
- 2.住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)の印紙税
-
3,000万円の物件の場合:1万円(2027年3月31日までの軽減措置適用時)




あれ?電子契約だと印紙税いらんのとちゃう?




その通りです!ネット銀行で電子契約を利用する場合は、印紙税が不要になります
都銀・地銀でも電子契約できる場合がありますが、代わりに電子契約サービス料として1万円程度かかることが多いです。
4.住宅ローン関連費用
住宅ローンを利用する際には、金融機関に支払う各種手数料が発生します。
主な費用には以下のようなものがあります。
| 融資事務手数料型の場合 | 融資金額 × 2.2%(税込) |
| 保証料型の場合 | 100万円あたり約2万円(借入期間35年の場合) |
| ローン事務取扱手数料 | 3万円〜5万円(ネット銀行では不要なことが多い) |
例えば、3,000万円のローンを融資事務手数料型で組む場合、3,000万円 × 2.2% = 66万円の費用がかかる計算になります。




金融機関によって手数料体系が全く違います。これはめちゃ大事なポイントなので、複数の金融機関を比較検討することをおすすめします




そんなに違うんや・・諸費用だけで100万円近く変わることもあるってこと?




同じ物件を買うにしても、不動産会社と金融機関の選び方で100万円以上変わることは普通にあります
また、諸費用込みでローンを組む「諸費用ローン」を利用する場合は、担保価値以上の借入になるため、金利が高くなったり審査が厳しくなったりする可能性があることも覚えておきましょう。
5.火災保険料・地震保険料
住宅ローンを利用する場合、火災保険への加入が必須条件となります。
火災保険は単に火災だけでなく、台風や落雷などの自然災害、水漏れや盗難なども補償の対象になります。
火災保険料は補償内容や契約期間によって異なりますが、2022年10月以降は最長契約期間が5年となり、5年一括払いで12万円〜25万円程度が目安です。
地震保険は火災保険とセットで加入することが一般的で、1年または5年の契約期間があります。




火災保険の費用を抑えるには、補償内容を必要最低限にしたり、不要な特約を外したりする方法があります。特に、洪水リスクのないエリアであれば水災補償を外すことで保険料を抑えられる可能性があります
6.その他の費用
上記以外にも、以下のような費用が発生することがあります。
| 固定資産税の日割り分 | 決済時に日割りで精算します。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、年の途中で購入する場合は購入日以降の分を売主に支払います。 |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に都道府県に支払う税金です。新築住宅の場合は軽減措置があり、3,000万円程度の建売住宅であれば、ほとんどかからないケースも多いです。 |
| ローン事務代行手数料 | 仲介会社によっては、住宅ローンの手続きをサポートする費用として10万円〜20万円程度請求するケースがあります。 |
| 引っ越し費用 | 新居への引っ越し費用も考慮する必要があります。4人家族の場合、通常期で11万円〜12万円、繁忙期(2月〜4月)では16万円〜17万円程度が平均とされています。 |
| エアコン・カーテンなどの費用 | 新築一戸建ての場合、エアコンやカーテンレール、テレビアンテナなどが付いていないことが多いため、これらの設置費用も考慮しておく必要があります。 |




ローン事務代行手数料は本来仲介手数料に含まれるべき業務内容です。仲介手数料を満額支払っているのに、さらにローン事務代行手数料を請求されるのはおかしいと思いませんか?




エアコンとかカーテンレールもついてへんの?それって結構な出費になりそう




新築一戸建ては、マンションと違ってカーテンレールやテレビアンテナが付いていないことが一般的です。この部分の費用も見落とさないように注意してください
諸費用が発生するタイミング
1.契約時に必要な費用
建売住宅の購入が決まり、売買契約を結ぶときに必要になる費用は以下の通りです。
| 手付金 | 物件価格の5〜10%程度が一般的ですが、新築建売の場合は100万円程度でも問題ないことが多いです。これは諸費用ではなく、最終的に物件価格の一部に充当されます。 |
| 印紙税(売買契約書) | 契約書に貼付する印紙代です。3,000万円の物件であれば1万円が必要です。 |
| 仲介手数料の半金 | 仲介会社によっては、契約時に仲介手数料の半額を支払うケースがあります。 |
2.引き渡し(決済)時に必要な費用
物件の引き渡し(決済)時には、最も多くの費用が発生します。
| 登記費用 | 表示登記費用・所有権移転登記・保存登記費用・抵当権設定登記費用などが含まれます |
| 印紙税(金銭消費貸借契約書) | 住宅ローン契約書に貼付する印紙代です |
| 住宅ローン関連費用 | 融資事務手数料や事務取扱手数料・保証料などが含まれます |
| 火災保険料・地震保険料 | 一括払いの場合、決済時に支払います |
| 仲介手数料の残金 | 契約時に半金を支払った場合、残りの半金を決済時に支払います |
| 固定資産税の日割り分 | 購入日以降の固定資産税を日割りで売主に支払います |




ほとんどの諸費用は、一番最後の決済の時に必要になります
手元に現金を用意しておく必要があるので、計画的に準備しておきましょう。
3.引き渡し後に必要な費用
物件の引き渡し後にも、以下のような費用が発生します。
| 不動産取得 | 不動産取得後6ヶ月〜1年の間に納税通知書が届き、支払います |
| 家具・家電購入費 | 特にエアコン、照明器具、カーテン、カーテンレールなどは新築住宅に付いていないことが多いため、別途購入する必要があります |
| テレビアンテナ工事費用 | 新築一戸建てにはアンテナが付いていないことが多いため、設置工事が必要です |
| 引っ越し費用 | 新居への引っ越し費用です。時期によって金額が大きく変わるため、繁忙期を避けると費用を抑えられます |
諸費用を安く抑えるポイント
1.不動産会社選び
仲介手数料は諸費用の中でも大きな割合を占めるため、どの不動産会社を通して購入するかで大きく金額が変わります。
以下のポイントを意識しましょう。
- 新築一戸建て建売住宅限定で仲介手数料が無料または割引になるサービスを提供している会社を探す
- 仲介手数料以外の名目で、ローン事務代行手数料・現況測量費などの追加費用を請求していないか確認する
- 不動産会社のサービス内容や評判も考慮する




同じ物件を購入する場合でも、不動産会社によって諸費用が100万円以上違うケースもあるため、慎重に選ぶことが重要です
2.金融機関選び
住宅ローンの手数料や保証料は、利用する金融機関によって異なります。
- 融資事務手数料型と保証料型のどちらが有利か比較する
- ネット銀行と都市銀行・地方銀行の違いを理解する(ネット銀行は事務手数料が不要だが、契約から決済までに時間がかかることが多い)
- 諸費用ローンを利用する場合、金利条件が悪くなる可能性があることを考慮する




手数料が安くても金利が高ければ長期的にはコスト高になる可能性があります。総返済額を含めたトータルコストで比較することが大切です
3.火災保険選び
火災保険料は、補償内容によって大きく変わります。
- 必要な補償内容を見極め、不要な特約を外す
- 水災リスクのないエリアであれば、水災補償を外すことで保険料を抑えられる可能性がある
- 複数の保険会社から見積もりを取り、比較検討する




不動産会社さんが保険も勧めてくるけど、それってお得なんかな?




特に不動産会社が保険代理店を兼ねている場合、すべての特約を含んだプランを提案されることが多いです。本当に必要な補償は何かを自分で判断することが重要です
貯蓄が少ない場合の対処法
マイホーム購入を考えているものの、諸費用を用意するための貯蓄が十分でない場合、以下のような対処法があります。
諸費用ローンの活用
多くの金融機関では、住宅ローンと合わせて諸費用も借りられる「諸費用ローン」を提供しています。
これを利用すれば、自己資金が少なくても住宅購入手続きを進められますが、以下の点に注意が必要です。
- 諸費用ローンを利用すると、担保価値以上の借入になるため、金利が上がる可能性がある
- 返済能力に不安ありと判断されて審査に落ちてしまうリスクがある
- 手付金など「現金での準備が原則」とされている費用もあり、最低限の現金は必要




諸費用ローンは便利ですが、金利面でのデメリットがあります。できれば諸費用は現金で用意するのが理想的です。それが難しい場合は、最低限必要な現金(手付金など)だけは準備しておきましょう




でも、貯金が少ないからどうしよう・・って人も多いんちゃうかな?




手付金は物件価格の5〜10%が一般的ですが、新築建売住宅の場合は100万円程度でも対応可能なケースが多いです。現金が少ない場合は、物件の契約前に不動産会社と交渉することも検討しましょう
また、引っ越し費用や家具・家電購入費などは、クレジットカードやリフォームローンなど別の借入手段を検討することも一つの方法です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
新築一戸建て(建売住宅)の購入には、物件価格の5〜10%程度の諸費用が別途必要になります。
3,000万円の物件であれば、約150万円〜300万円の諸費用を見込んでおく必要があります。
諸費用の内訳としては、仲介手数料・登記費用・印紙税・住宅ローン関連費用・火災保険料などがあり、これらは契約時、引き渡し時、引き渡し後など様々なタイミングで発生します。
- 仲介手数料の割引がある不動産会社を選ぶ
- 住宅ローンの手数料体系を比較し、自分に合った金融機関を選ぶ
- 火災保険は必要な補償内容に絞り、複数社から見積もりを取る




当社ゼロ仲介では新築一戸建ての仲介手数料が0円になるサービスを提供しています。3,000万円の物件であれば、仲介手数料約105万円が丸々浮くことになります
マイホーム購入は人生の中でも大きな買い物です。物件価格だけでなく諸費用も含めた全体の資金計画をしっかり立て、無理のない範囲で理想の住まいを手に入れましょう。




一都三県(東京・神奈川・千葉・埼玉)や近畿圏で新築一戸建てをお探しの方は、ぜひゼロ仲介にお問い合わせください。仲介手数料0円で、諸費用を大幅に抑えたマイホーム購入をサポートいたします
この記事を参考に、少しでもかしこく住宅購入ができるよう応援しています!